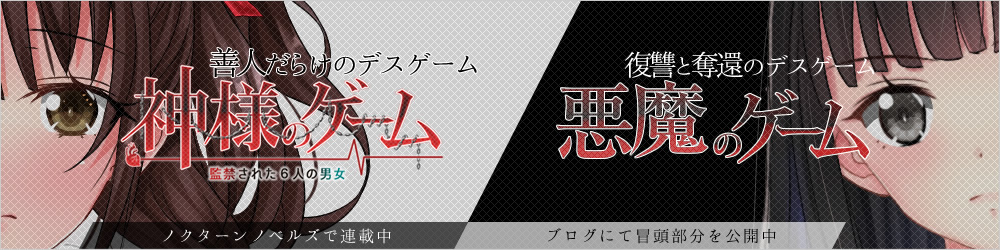扉をくぐった先は馴染みのある場所に繋がっていた。
「ここは……」
怪訝に呟き、琴子がコンパスの針のように身体を一巡させて周囲を見渡す。
灰茶に渇いた漠々たる荒地。重い薄墨色で幾重にも覆われた空。そこに浮かぶ雲は現実と変わらぬ白色だが、光源となっている太陽らしきモノもまた、蛍光灯のような歪な白き光を放っていた。
目に映る範囲に建造物はおろか、山や丘、植物の一本すら見つからない。果てしなく続く荒野の先に地平線が見えるだけだ。
「初めてお兄様とお会いした時に見せていただいた、映像の場所、ですよね?」
「だな、爺さんが造った不思議世界だ」
やはり、と琴子が得心したように顎を引く。きっと彼女は白黒写真の世界に迷い込んだような錯覚を覚えているだろう。
無論、ここで短くない時を過ごした壮士は驚きはしない。が、あまり良い気分ではなかった。
壮士にとって罪の象徴とも言える場所だ。
探して回った一馬と心を見つけ、しかし彼らが苦しむ様をただ眺めることしかできず、挙句、無二の人が連れ去られるのを止められなかったばかりか、兄と共に悪行を犯した――、そんな、今に繋がる起点となる場所だ。
「あれも以前と同じですか?」
琴子のそれは質問の体裁こそ取っていたが、恐らくこちらの答えを予期してのものだ。
壮士は彼女の予感を裏付けるように首を振り、
「いや、あれは無かった」
二人の視線の先。モノクロに支配された世界のなかで異彩を放つ物が二つある。
赤い扉と青い扉。
赤の方は凝固した血のような気味の悪い色で、青の方も鮮やかな青ではなくやや紫みを帯びた深い青。こちらもあまり良いイメージの湧かない不吉な色だった。
扉の周囲に壁はない。二枚のそれは地面から生えたように単体で存立していた。
そしてもう一つ。この扉が意味するところを知っているであろう老人が一人。
「ようこそ死地へ――。奈津嬢との別れは済みましたかな?」
「まずは説明を受けましょう」
悪魔の問いを無視し、さっさと本題に入れとばかりに顎をしゃくる琴子。
彼女に続き、壮士は小さく肩をすくめて同意見である旨を悪魔に示した。
既に気になることがいくつもある。扉の先がどうしてここに繋がっていたのか、ここがゲームが行われる会場なのか、会場であるならどうして壮士と琴子しかいないのか、悪魔の背後にある扉は何なのか。挙げればキリがない。
なのでまずは説明を受ける。死地に踏み込んだ以上、兵卒である壮士は参謀殿に服従なのだ。
老人は彫りの深いシワをより深く頬に刻みながら微笑み、
「無駄を排す嬢の姿勢。実に好ましく存じます」
では早速――、と悪魔は語り始めた。
「まずはゲームの概要からお話しましょう。悪魔のゲームとは単一のゲームを指すものではありません。趣の異なるゲーム群の総称です。お二人にはそのすべてに於いて勝利を目指していただかねばなりません」
そこまで聞いたところで、琴子が顎に手を添えて言う。
「つまり悪魔のゲームとは勝ち抜き戦であると。ゲームを経る度にプレイヤーが脱落して行き、それを繰り返すことで、最終的に相手方プレイヤーを殲滅した側の勝利となる。そういう認識で構いませんか?」
「構いません。が、誤解がないよう補足しておきましょう。壮士殿と琴子嬢は今こうして揃って説明を受けておられますが、契約時に申し上げた通り、プレイヤーとしてはあくまでも別個の扱いです。なれどこの勝ち抜き戦。多対多で行われるケースがございます」
悪魔のそれを受け、壮士と琴子は同時に眉をひそめた。
壮士と琴子はいま一緒にいるが、個別のプレイヤーとしてカウントされる。それはいい。あらかじめ分かっていたことだ。
しかしそれは建前に過ぎないのだ。
勿論、一対一で行われるゲームであれば選択の余地はないだろう。壮士であれ、琴子であれ、独力で勝利を目指さねばならない。
しかしながら、多対多のゲームであれば話は変わる。いくら別個の扱いだと言われたところで、壮士と琴子が当該ゲームに同時に参加してた場合、必ず協調して事に当たる。
故に別個のプレイヤーというのは建前に過ぎず、実態として二人はペアなのだ。
それらを踏まえると、先ほどの悪魔の説明に引っ掛かる点が出てくる。
「だったら、なんでこの場所に俺たちしかいないんだ?」
悪魔の説明に拠れば、最初からこのゲームは集団戦を予定している。にも関わらず、この場に居る悪魔側のプレイヤーは壮士と琴子のみだ。
言うまでもなく壮士と琴子の最終目標は神殺しだ。しかしそれは契約で定められた要件に過ぎず、悪魔のゲームに於ける勝利条件は、神側のプレイヤーを殲滅することにある。
多対多――即ち陣営対陣営という構図で殺し合うゲームを予定しているなら、壮士と琴子のそれと同様、悪魔の側に属するプレイヤー全員で協調関係を築くべきなのだ。
故に、この場に壮士と琴子しか居ないというのは合点がいかない。
悪魔はこちら側の親玉だ。彼が自陣の勝利を目指し、且つ集団戦があることを織り込んでいるなら、この場に悪魔側のプレイヤーを集めて然るべき。
さらに言えば、多対多が予定されている事実そのものが、個人参加という意義を薄めてしまっている。元よりこの殺し合いは一人の勝者ではなく陣営の勝利を目指す物だ。それぞれの陣営が群として挑む方が理に適っている。
意外なことに、壮士の疑問に答えを示したのは悪魔ではなく琴子だった。
「恐らくそれも込みなのでしょう」
「込み……?」
わけがわからず壮士が問うと、琴子は悪魔をひと睨みしてからこちらに目を向けて、
「多対多。その集団戦とやらが、敵味方入り乱れての殺し合いになるという意味です。私が契約したとき、悪魔が言っていた言葉を覚えていますか?」
「契約のとき……、あ……」
確かあのとき、琴子と悪魔の間でこんなやり取りがあった。
――悪魔側のプレイヤー間で協調するのは自由、という理解でいいですか?
――構いません。できるなら、ですが。
協調は自由。ただし、それが実現できるならと悪魔は答えた。
つまるところ、
「……敵と味方の判別は自分でやれ。それ込みの集団戦ってことか」
「そいうことかと。味方が味方と分からなければ、プレイヤーはやはり個です。個人参加を強調する理由、そしてこの場所に私たちしかいないことにも説明がつきます」
琴子の推察は悪魔の一言で肯定された。
「ご明察です」
敵味方の区別がつかない――。この事実は軽くない。
同士討ちが起こっても何らおかしくなく、逆に誤解したまま、あるいは騙されたまま、敵と手を結んでしまう事だって起こり得るだろう。
もしその集団戦とやらが、いわゆるバトルロイヤルのような分かりやすいゲームならまだいい。実際に殺れるかどうかは別として、最悪敵味方関係なく皆殺しにするという手段が取れる。
しかしそれがカードゲームやテーブルゲーム、神様のゲームのような、暴力でどうこうなるような質のものでない場合、プレイヤーの負うリスクは一気に跳ね上がる。
プレイヤー同士が接触し、腹の内を探り、駆け引き取引するなかで、その相手がまず敵なのか味方なのかを切り分けねばならないのだ。心理戦という側面での難易度は桁違いだ。
ならば、悪魔と神はどうしてこんな困難をプレイヤーに強いるのか。
決まっている――。
(クソ野郎どもが。悪趣味にもほどがある)
面白いからだ。楽しいからだ。
神と悪魔がただ白黒つけたいだけならこんな真似をする筈がない。自陣の勝利に必要ない要素だ。
この外道どもは、自分の駒であろうと相手の駒であろうと関係なしに、人間たちが疑心暗鬼に陥り右往左往する様を鑑賞して愉しむつもりなのだ。
しかし、
「続けてくれ」
壮士は燻る怒りに蓋をして、以降の会話に割って入らぬことにした。
先のやり取り一つ見ても明らかだ。琴子に任せておけばいい。壮士がいちいち問わずとも彼女が回答を導き出してくれる。
横槍を入れない方が参謀殿もやりやすいだろう。
そんな壮士を横目で見ながら、琴子が言う。
「今の話に関連して尋ねたいことがあるのですが、質疑は後回しにした方が良いですか?」
「いいえ、都度お受けしましょう」
では、と琴子は頷いて、
「敵味方の線引き自体がゲームの一要素であることは理解しました。しかしそれでは、貴方が以前に約定した『プレイヤー間の公平性を保つ』という点に齟齬が生じます。
私とお兄様は最初から協力関係にあります。いくら形式的に個別を謳ったところで、実態としてペアでの参加。そんな二人が同じ場所で説明を受けているのです。これは真に単独で参加しているプレイヤーに対する明らかな不利益でしょう」
「なるほど、一理あります。それで質問とは?」
「私たちと同様の存在が神の陣営にも居るのか――」
そこまで聞いても今ひとつ要領を得ない壮士だったが、
「居るとすれば“群れ”を成しているのかハッキリさせておきたい」
続けて出た琴子の言葉を聞いて、彼女の意図したところを理解できた。
前段の琴子の指摘は言葉のままだ。事実上ペアで参加している壮士と琴子は、完全に一人きりで参加しているプレイヤーたちにとって不公平な存在に違いない。
だが、この点は必ずしも齟齬であるとは言い切れないだろう。
契約時に悪魔が約定のは二点。
・たとえペアで参加しても扱いは個別となる。
・陣営内で協調するのは自由、ただし自助努力で以って行うこと。
神と悪魔。両陣営ともに事実上のペア参加が認められているなら、公平性は保たれている。そも悪魔は徒党を組むことを禁じていないし、最初から協力関係にあった壮士と琴子の参加を認めている。むしろ琴子を誘ったのは悪魔本人だ。
それゆえ、たとえ単独で参加しているプレイヤーに不利益があろうと、ペアでの参加が認められている以上、彼らは甘んじてそのリスクを負わねばなるまい。それが嫌なら複数名で参加すればいいのだ。
その上で琴子が危惧したのは、こちらと同様の別の存在が群れている、即ち集団である可能性だ。
彼女が明確にしておきたいと思ったのも無理ない。神側がペアではなく三名・四名・五名と群れていて、且つその状況下で集団戦が行われるとなれば著しい脅威だ。
琴子の問いに、悪魔は得心したように一度頷くと、簡潔に答えを示した。
「結論から申し上げれば神の側にも存在します。無論、こちら側にも。ただし、その数は群れというほどのことはありません。最大で三名です」
その三名が誰を指したものなのか――、知る由もない琴子は軽く眉をひそめて、
「……意外とすんなり答えるのですね」
「答えたところで勝敗に影響はないでしょう。嬢の懸念は理解できるものです」
「結構。続けてください」
悪魔は髭を撫で付けながら暫く黙考して、
「概要としては以上ですな。ここからは具体的な手順をご説明します。が、その前に。お二人に紹介したい者たちがいます」
おいでなさい、と悪魔が振り返ったのと同時に、二つの扉が音もなく開いた。
壮士はホルスターへ手を伸ばしながら一歩前に出て、琴子を庇うべく己の半身で彼女を遮る。しかし、琴子は無用とばかりにこちらの腕に触れると、壮士を優しく押しのけて二歩前に出た。
それから琴子は愉しげに口元を歪め、扉から出てきた二人に告げた。
「はじめまして人外さん。円成寺琴子と申します」
第一声がそれか、と思わないでもない壮士だったが、琴子がそんな言葉を口走ったのも無理からぬことだろう。
扉から出てきたのは二人の少女。彼女らはひと目見て人間でないと分かる容姿を備えていた。
「どもー! はじめましてー!」
「これはご丁寧に」
赤の扉から出てきた少女がニパっと笑い、続いて青の扉から出てきた少女が美しい所作で腰を折った。
身長はおおよそ百六十センチ弱ぐらい。大きな瞳に色素の薄い桃色の唇、彫りの浅い顔立ちは幼さと愛らしさを感じさせる。
瓜二つの顔をした二人は、いずれも腰の長さまである長髪を一本のおさげに結っているが、髪の色は異なる。元気そうな赤から出てきた少女が金色、清楚な感じの青から出てきた少女が銀色。金色の瞳はルビーのように赤く、銀色の瞳はサファイアのような青さというのも違いだ。
白と黒を基調としたゴシック調のドレスは、造形こそやや派手だが華美な装飾は施されておらず二人の存在感を際立たせていた。
その他で目を引くのは尖った耳。悪魔で見慣れているとはいえ、それだけ切り取っても彼女らが人外であることは明らかだった。
悪魔が脇に立つ二人に目配せして言う。
「ご挨拶を」
先に口を開いたのはルビー色の瞳を持つ少女。
「どもどもー! “赤の部屋”を担当する神威《カムイ》だよ! カムカムって呼んでね!」
続いてサファイア色の瞳を持つ少女が腰を折り、
「桐山様、円成寺様、お初にお目にかかります。“青の部屋”を担当させていただきます魔阿《マア》と申します。カムイと違い、私はお二人の案内役も兼任させていただきます。どうぞ私のことはマアとお呼び捨てください」
悪魔は好々爺のように朗らかに笑って後を引き継ぐ。
「挨拶が済んだところで説明を再開しましょう。これより壮士殿と琴子嬢にはゲームに挑んでいただくわけですが、その会場となるのがこの扉の向こう、赤の部屋と青の部屋となります。神威と魔阿は各部屋で行われるゲームを取り仕切る役目を担います。ディーラーのようなものとお考えください。
無論これもプレイヤー間で公平性を保つ為の措置です。
私と神はそれぞれの陣営の頭《かしら》であると同時にゲームの主催者。その我々が個々のゲームを仕切り、まして勝敗の判定をするとなれば皆様の不興を買いましょう。故に中立を旨とする二人を置くこととした次第です」
「なるほど……」
ぼんやりとそう言って、琴子が沈黙した。
そんな参謀殿を横目に眺めつつ、壮士は頭のなかで悪魔の言葉を吟味する。
(理屈はわからないでもないけどな)
仮に壮士が参加したゲームで何かしらの判定が必要になったとする。
その判定を神が行うとなれば壮士は間違いなく不満を訴えるだろう。
神は敵の頭目だ。なにをどう考えたってあの邪神が悪魔側のプレイヤーに利する判定を下すと思えない。逆もまた真なりだ。神側のプレイヤーも悪魔の裁定を容れないだろう。
だから中立公正にジャッジする第三者を置く。その措置は理に適ったものだと思う。
しかしそれは、このカムイとマアという少女が信用に値する人物であることが大前提だ。
この二人。ハッキリ言って名前からして胡散臭い。カムイという名はあからさまに『神』の字が含まれているし、マアにしてもどういう字を書くのかわからないが、『マ』という響きが『魔』を意味するであろうことは容易に想像がつくというものだ。
加えて、カムイの軽薄な言葉遣いにユルイ態度、マアの丁寧な口調と物腰。明らかに親玉の性質と似通っている。
これでは神と悪魔が判定を下すのと何も変わらない――、壮士じゃなくともそう思うに違いない。
無論、琴子はこれらの点を追求するはず。
壮士はそう信じて疑わなかった――が、
「…………」
琴子が口を開かない。
顎に手を添えた体勢で瞼を閉じ、何かを考え続けていた。
(おいおい、頼むぞ……)
そんな彼女の様子を見て、壮士は胸騒ぎを覚えた。
だって壮士ですら問題点が見えている。悪魔に対して何をどう問い詰めるべきか、そのセリフすら頭に描けているのだ。
なのにあの、やたらと頭が切れる琴子がまだ考えている。これが嫌な予感を覚えずにいられようか。
ふと悪魔に目をやると、
「ほう」
こちらと同じ考えに至ったのか、老人は興味深そうな顔で琴子を観察していた。
神威は不思議そうな顔で首をひねっていて、魔阿は腹の前で手を組み柔らかな微笑を浮かべるのみ。
「悪魔」
「なんでしょう」
時間にしてみればほんの一分程度。
しかし不可解な沈黙の時を経て、ようやく琴子が口を開いた。
「こちらのお二人にいくつか尋ねたいことがあるのですが、話して構いませんか?」
「勿論です。私に許可を得るまでもないことです」
言って悪魔は柔らかに微笑むと、神威と魔阿を残して数歩横に歩き、脇に控えた。
「マアさん、でしたか。貴女にお尋ねします」
「はい、円成寺様。なんなりとお聞きください」
「ありがとう。まずは貴女の成り立ちを教えてください。貴女たちは天界だとか魔界だとか、そんなオカルト世界から来られたのですか?」
「いいえ、円成寺様。この世に天界魔界などという場所はございません」
「まあ、そうなのですか」
「はい。私は創主様と神様によって創られました。こちらのカムイも同様です」
魔阿の答えに、琴子は分かりやすく驚きを顔に貼り付けると、横目で悪魔を睨みつけて、
「貴方……、生命の創造までできるのですか?」
「嬢が思われるほど簡単ではないのですが。一応は」
化け物が、と琴子は口のなかで呟き、今一度魔阿に目をやる。
「念の為に確認しておきます。創主とは悪魔のことですね?」
「はい、私を創ってくださった方ですので創主様とお呼びしています」
魔阿が微笑みながらそう答えると、琴子は神威に向き直り、
「カムイさんにお尋ねします。貴女は神と悪魔のことをなんと呼びますか?」
「呼びかた? 神様はママで、じーちゃはじーちゃだよ?」
キョトンとした顔で答えたカムイは、その容姿も相まって実に愛らしい。
琴子は「そうですか」と微笑みを返すと、ふたたび視線を魔阿に向けた。
(……?)
そこで、黙って成り行きを見守っていた壮士はふと気づく。
琴子の右手が腰の裏に回されていて――、
(ハンドサイン?)
拳を緩く握り、人差し指だけを軽く浮かせ、浮かせた指の横腹に親指が添えられた。
意味するところは『壮士に任せる』だ。
(俺に任せる? なにを?)
皆目意味が分からず眉をひそめる壮士。
一方、琴子と魔阿の会話が続けられる。
「マアさんにお尋ねします。先ほど貴女は私たちの案内役を兼任すると言っていましたが、案内役とはどのようなお役目なのでしょうか」
「はい。案内役とは、プレイヤーが円滑にゲームに臨めるようオペレーションを担う者を指します。たとえば円成寺様が一つのゲームに勝利され次のゲームに挑まれる場合、青の部屋と赤の部屋どちらで次のゲームが行われるか、私がご案内します。また、お二人が順調に勝ち進まれた際には、ゲーム全体の進捗状況なども報告させていただくことになろうかと思います。悪魔側のプレイヤーには私が、神様側のプレイヤーにはカムイが、それぞれ案内役を努めるよう仰せつかっております」
「そういうことでしたか」
琴子は頷きつつ右手の形を変えた。
固く拳を握り、それから人差し指と中指を立て、続けて中指だけを折りたたむ。
意味するところは『右』だ。
「再度カムイさんにお尋ねしましょう」
「なあに? 質問はいいんだけど、めんどくさいからまとめて聞いてほしーなー」
コツコツと渇いた地面を足で小突く神威。
琴子は「ごめんなさい」と侘びながら、さらに右手を動かした。
彼女の手は目一杯ひろげられ――、
「カムイさんは赤の部屋においてゲームのディーラーを努めるとのことですが、悪魔の陣営である私たちにも公正にジャッジしていただけるのでしょうか」
「それー。さっきじーちゃが説明したでしょー?」
「手間を取らせて申し訳ありません。どうしても直接カムイさんの口から聞きたくて」
「あー、はいはい。お前ちょっと面倒くさいやつだね。心配しなくたってカムもマアもズルしたりしないって。これでいい?」
「はい、ありがとうございます」
そう琴子が微笑んだと同時に、拳が握り込まれハンドサインは完成した。
――シュダンハトワナイ、ミギヲ、コロセ。
壮士の脳は『なぜ』の二文字に埋め尽くされた。
「―――――」
なぜ、何故、ナゼ、なぜ、何故、どうして――。
何をどうすれば、この時この場所で、この娘を、殺すという結論になる。
「……ッ」
壮士の脳は押し寄せる不理解の波に翻弄されながら、並行して至上の命令を実行に移すべく、肉体に信号を放った。
服従の命を受けた肉体は万の数を繰り返した経験を元に、壮士の右手を最小最速でホルスターへ導く。そうして届いた右手は、未だについてこない意識を置き去りにして、得物を引き抜くと同時に安全装置を解除。
壮士本人も気づかぬまま、銃口は対象に向けて固定されていた。
「え……」
目を剥き、神威が驚愕を顔に貼り付けた刹那。
「ズルはしない、ですか」
琴子は小馬鹿にするように鼻を鳴らし、硬直する少女に向けて冷然と告げた。
「信用できません」
直後、灰色の世界に銃声が響いた。