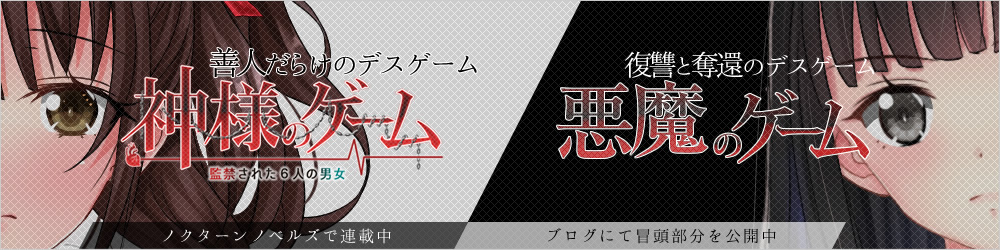兄妹の日から三日後。
壮士と琴子、奈津の三人は悪魔のゲームに臨むべく帰国の途につこうとしていた。
グアム国際空港、旅客ターミナル。
壮士は人懐っこい笑顔を浮かべて、多くの外国人が行き交う様を一巡した。
思えば三ヶ月前、拉致同然に連れられて来られた時には随分と物怖じしたものだ。
しかし今、いざこの地を離れるとなるといくらかの寂寥を覚える。
それも一つの成長なのだと思いたい。
壮士はそんな感慨を覚えつつ、見送りに来てくれたお師匠様に右手を差し出した。
「世話になった」
「おう」
パンという小気味よい音と共に、ロバートがガッチリとこちらの手を握り返す。
節の太いこれぞまさに漢《おとこ》といった感じの手。幾度となくぶん殴られたこの手は、壮士が目指した標《しるべ》の一つであり、イチ男児としての憧れでもあった。
壮士は目一杯の感謝を込めて言う。
「最高のお師匠さんだった」
「お前もなかなかいい弟子だったよ。中身はカスだけどな」
「カスはてめえだろうが」
ニヤリと笑い、壮士とロバートはほどいた右手を拳に変えてバンプのジェスチャー。
日々ロバートにしごかれ、恨みをつのらせ、時には血だるまにされたこともあったけれど、今となっては良い思い出だ。
ここで過ごした理不尽な毎日は、確かな技能、タフな肉体と精神、そして教養と知恵を授けてくれた。
多少なりとも自信を持ってこの日を迎えられたのは、ロバートや講師の皆が鍛え上げてくれたお陰だ。
「ありがとう」
「礼はいらん。ギャラの分だけ仕事をしただけだ」
言って、迷惑そうに手を振るロバート。
性格に難のある彼はしかし、壮士にとってはもう一人の兄のようなものだ。
「ロブ」
「ああ、コトコ」
微笑み、そっと手を広げた琴子を、ロバートが柔らかくハグする。
ロバートはトントンと琴子の背を二度三度叩いてから抱擁を解き、
「今度は遊びに来い」
「近い内に必ず。もちろんお兄様と一緒に」
「待ってるよ」
「あと、今度来るときには私のフィアンセと親友を紹介しましょう」
「おお、そりゃ楽しみだ」
オーバーリアクション気味に手を持ち上げ、目を丸くするロバート。
続けて彼は名残を惜しむように琴子の頭をポンポンと撫で、
「悪いがコトコ。ちょっとだけ外してくれないか。ソージに話したいことがあるんだ」
「もちろん。私は奈津の様子を見てきましょう」
琴子は軽く頭を傾けて、カウンターで手続きをしている奈津の元へ向かった。
壮士は離れていく琴子の背を視界の端に収めつつ、
「この別れ際にどうしたよ」
「まあ、話ってほどのことでもないんだ」
首をひねりながら言った壮士に、ロバートは腕組みしつつ悩む素振りを見せて、
「実は昨晩、アクマだっていう爺さんが訪ねてきてな」
「へえ……」
予想だにしなかったロバートの告白を受け、壮士は深々と眉間にシワを刻んだ。
悪魔の意図を図りかねる。なにせもう帰国しようかというタイミングでの来訪だ。
いまさらロバートにどうアプローチしたところで、こちらに影響があるとは思えない。が、裏でコソコソと動かれるのはいい気がしないし、警戒だってする。
ともあれ、ロバートの様子を見る限り大事には至らなかったのだろう。
そんな風に壮士は安堵しつつ、
「さすがのロブもビックリしただろ」
「そりゃもう驚いたさ。突然ベッドの横に立ってたんだぞ? なんか耳尖ってるし」
「はは、だよな」
「思わず枕に仕込んでたナイフで腹割いちまったよ」
「は、はら割いた……?」
なにこのハゲ。怖すぎる。
「だって怖かったし」
「怖いなら逃げろよ。なんで戦うんだ……」
「相手はモンスターだぞ? 殺らなきゃ殺られるって思うだろうが」
「いやな? 化け物相手だからこそ普通は逃げるんだって」
「かなり動揺しててな……。そこまで頭が回らなかった」
「そっか……。なら仕方ないよな」
この黒人男性は、動揺してたら有無を言わさず相手の腹を掻っ捌くらしい。
今ひとつ現実味に欠ける悪魔なんかより、ロバートの方がよほど怖かった。
「だいたい、なんで枕にナイフなんて仕込んでんだよ」
「身を護るために決まってるだろ。世の中物騒だからな」
「物騒なのはロブだろ。いつの時代に生きてんだよ……」
常在戦場を地で行くハゲ。
よくもまあ人のことを好戦的などと言えたものだ、と呆れる壮士である。
「で、ナイフぶっ刺した結果、血の一滴ぐらいは出たの?」
「いや、出なかった。といより手応えがなかった」
「ああ、そんな感じなんだ。やっぱあのジジイ人外だな。とにかく無事で良かったよ。こうしてピンピンしてるってことは、爺さん怒らなかったんだろう?」
「まあな。怒るどころかあの爺さん『どうぞ気の済むまでお試しください』って笑ってたよ」
聞けば、悪魔はただ壮士と琴子を鍛えてくれた礼を言いに現れただけのようで。
ロバートはそれらを話し終えると、深々と溜息をつき、
「現物を見せられちゃ信じるしかない。今まで軽く考えてて悪かったな」
「そんなこと気にしてたのか。謝ることないって。信じろっていう方が無理な話なんだから」
「それでも信じてやれば別のやり方もあっただろうにって思ってな」
「いいって。ロブは十分良くしてくれたじゃないか。感謝してる。話ってそれだけ?」
義理堅いお師匠様に苦笑する壮士。――と、突然ロバートにハグされた。
「ソージ」
「ロブ……?」
アメリカ人がごく普通に行うであろう親愛を示すその行為は、生粋の日本人、それも外国デビューから日の浅い壮士にはどうにも照れくさく感じてしまう。
自分も腕を回すべきだろうかと考えている内に、ロバートはバッシバッシと背中を叩いてきて、
「死ぬなよ」
「…………」
耳元で聞こえる彼の声は、これまで聞いたどの時よりも優しい響きを帯びていて、故に壮士は口元を緩ませながら静かに顎を引いた。
「コトコを守れ。心配ない、お前ならやれるさ」
「任せてくれ」
壮士は力強くそう答え、ロバートの背中に手を回し、お返しとばかりに彼の背を叩いた。
やがて抱擁を解いた二人は、今一度拳をぶつけ合って、
「迷うな。躊躇わず殺れ。あと――」
「琴子の命令には無条件でイエス、だろう?」
「忘れるなよ?」
言って、ロバートはおおらかに笑いながらこちらの頭を小突くと、これが最後とばかりに右手を差し出した。
壮士は不敵な笑みを顔に貼り付けつつ、シッカリと彼の手を握り、
「勝ってくる」
「おう、次はフィアンセちゃんを連れてこい」
こうして三ヶ月強を費やした、人殺しの練習は終わりを告げたのだ。
◆◇◆
日本に舞い戻ったその日の夜。
壮士は久しぶりの祖国を満喫する暇もなく、早々に困り果てていた。
日のドップリと暮れた22時過ぎ。
場所は壮士の住処である一馬のマンション。
「帰れ」
たしなめるような声でそう言って、壮士は対面に座る自称妹を睨みつけた。
しかし拒絶された妹様は、ここを一歩も動くものかとばかりに腕を組んで、
「嫌です」
ならばと壮士は、最近ちょっとだけデレるようになったメイドさんに矛先を変える。
台所でお茶の準備をしている彼女の背に向け、先ほどよりもお願いの色を濃くした声で言う。
「帰ってくれ」
「嫌です」
こちらを振り返ることなく、一蹴するなっちゃん。
やむなく壮士は矛先を妹に戻した。
「なあ……」
「嫌、です」
睨み合う兄と妹。そして我関せずの自称姉。
壮士は憤懣やるかたない顔で立ち上がると、ズビシと玄関を指差し、
「帰れ!」
「嫌です」
「嫌です」
阿吽の呼吸で拒絶する琴子と奈津である。
「頼むから帰ってくれよ……」
「帰りません。お兄様がなんと言われようと私はここに住みます」
約束の日まで残すところあと七日。
それまで一緒にここに住むと言い出した二人が帰ってくれないのだ。
「もっと早く気づいていれば……」
壮士は崩れるようにソファに腰を沈めて、ここに至るまでの経緯を振り返った。
といっても、それほど大した話ではない。
日本に到着した後、琴子の『お家までお送りします』という善意溢れる言葉に便乗して、壮士は仮の住まいである一馬のマンションに向かった。
滞りなくマンションに着き、壮士が『じゃあまた』と手を上げると、
『久しぶりに一馬様のお部屋を見とうございます。お茶を一杯ご馳走してくださいませんか』
そんな健気な妹のお願いに、壮士は二つ返事で了承。
奈津を加えた三人で長らく空けていたマンションに入った。
ところが、
『あれ……?』
入ってみると、何かがおかしい。
様変わりしているわけではないのだが、微妙に家具の位置が変わっていたり、覚えのない小物が部屋のあちこちに点在していた。
この時点で既にきな臭いモノを感じていた壮士だが、一度いいよと言った手前、いまさら帰れとは言えなかった。いかにも日本人的発想である。
そこからは完全に琴子と奈津のペースだ。
茶を淹れるやいなや奈津はすっくと立ち上がり、
『じゃあ晩御飯の買い物に行ってきます』
『では私はご飯を炊いておきましょう』
『お前ら飯食って帰るの……?』
『壮君はなに食べたいですか?』
『え……、まあ、グアムと違ってこっちはまだ冬だし、鍋とか……?』
『いいですね、お鍋。奈津、そうしましょう』
『はいはい。琴子は普段お鍋を食べる機会なんてないもんね』
『楽しみですっ。みんなで一つの鍋をつつく、これぞまさに家族の団らん。素敵です』
という感じで奈津はスーパーへ出かけ、琴子はご飯を炊き始めた。
お陰様で鍋はすこぶる旨かったのだが、しかし、
「茶の一杯がなんで住むって話になるんだ……」
「私は帰りたいんですよ?」
言いながらテーブルに茶を並べてゆく奈津。
どうも、と壮士は緑茶をすすりつつ、
「なら帰ってくれ」
「私が帰ったら二人きりになっちゃうじゃないですか。そしたら壮君、琴子を襲うでしょう?」
「なんて無礼なメイドだ。俺をなんだと思ってる」
「エロい、野郎、だと思ってます」
「あのな……」
「わたし忘れてませんから」
「? なんの話だ」
「前に私のこと組み伏せて胸揉みしだくって脅したでしょう?」
「あんなの冗談に決まってるだろ」
「じゃあ試してみます?」
ほら、と言って奈津が控えめな胸を突き出してきた。
なので壮士は遠慮なく揉んだ。そしたらビンタされた。意味がわからない。
「壮君サイテーです。知ってましたけどっ」
「お、それ。心とおんなじセリフだ」
「だったらなんですか……。私はときどき、お兄様が本当に一馬様の弟君か疑うことがあります……」
そう言って、呆れ顔で嘆息する琴子だった。
出会った当初は一馬の弟と信じて疑わないみたいなこと言っていたのに、随分と評価が下がってしまったものである。
ともあれ壮士としては、琴子はいささか兄のことを過大評価していると思うわけで、
「いやいや、今のは兄貴だって揉むよ?」
「一馬様はそんなことしませんっ」
「お前がそう思うならいいけど……。あとで幻滅することになっても知らないからな」
「余計なお世話です」
頬を膨らませた琴子に、「とにかく」と壮士は会話を軌道修正。
「いいから帰れって。長いこと日本を離れてたんだ。親も心配してんだろ」
「お母様は死にました」
「初っ端からキッツイ返しを……。お義父さんはいるじゃないか。仲は悪くないんだろう?」
「義父《ちち》のことなら問題ありません。頻繁に電話で話していますし、会いたくなったら直ぐに会いに行けます」
「なら尚さらここに住む必要ないだろ。直ぐに来れるんだから」
「お兄様は何が気に食わないのですか?」
「いや、気に食わないとかじゃなくて……。年頃の娘が一人暮らししてる男の家に転がり込むのは色々と問題あるだろ。デカイ別荘で暮らしてた時とは違うんだ。ここって狭めの1LDKだぞ?」
「リリィちゃんとにゃむにゃむできないし?」
「なっちゃんは黙ってろ」
「壮君、リリィちゃん持って帰ってきてますよね?」
「! なんでそれをっ!?」
「バレてないとでも思ってたんですか? なっちゃんはお見通しです」
「くっ……」
「そちらについてもご心配なく。私たちも四六時中家にいるわけではありません。お一人の時に思う存分励んでくださって結構です。寝床はお布団を敷けば十分。生活空間を共有するのもお兄様であれば苦ではありません。なにを気遣う必要がありましょうか。お兄様と私は兄妹です。奈津とだって下世話な話すらできる間柄ではありませんか」
「こいつら……」
やはり阿吽の呼吸で攻め立ててくる姉妹だった。
これも出会った当初と随分と様変わりしたことで、プライベートの時間に限ってのことではあるが、奈津は違和感なく琴子を呼び捨てにするようになったし、お姉さんぽく振る舞うようにもなった。
きっと知らぬ人が見ても、ちょっと言葉遣いが特殊なだけの仲の良い姉妹に見えるだろう。
それは壮士にとっても喜ばしいことではあるが、
「わかった。そこまで言うならお前らはここに住め。俺は実家に帰る」
「それでは意味がありません」
「なんで。兄貴の部屋に住みたいんだろう?」
「違います。いえ、それも理由の一つですが、約束の日まで残り一週間なのですよ? サインの確認や物資の選別など、一緒に取り組まなければならないことがあるでしょう?」
「そんなの何時間かあれば済むことだろ。一緒に暮らさなくたって問題ない」
そこまで言って、壮士はふと思った。
もうそろそろ琴子は気づいてくれただろうか。
一緒に暮らすのは色々と問題がある、そう感じることに嘘はない。
彼女の義父も心配しているだろう。世間体だって悪い。
だが一週間が経ったその時、壮士と琴子は生きているかすら不確かだ。
そう思えば、いま話しているあれもこれもすべて些末なこと。
それが分かっていて尚、どうして壮士が頑なに拒むのか。
「嘘は良くないぞ。琴子」
「嘘……?」
願わくば、もうそろそろこの子にも理解してもらいたい。
桐山壮士という男は曲がった愛情表現を是としている面倒な奴なのだ。
「あー……」
ゲスい顔を貼り付けたこちらを見て、姉の方が先に察したようで。
奈津は処置なしとでも言わんばかりに大きく溜息をつくと、琴子の頭にポンと手を載せて。
「なんか壮君もの欲しそうな顔してるし、言ってあげたら?」
「む……」
その援護射撃で琴子も気づいたようだ。
琴子はいくらか頬を朱に染めて、恨みがましい目で壮士を睨み、
「勝負の行方がどうであれ。間もなく私は記憶を奪われてしまいます」
うん、と壮士は目尻を下げて顎を引く。
すると琴子は一段と顔を赤くして、さながら辱めを受けているような顔を作り、
「だからその……、私にとってこの一週間は……とても貴重な時間なのです」
普段では決して見られない歯切れの悪い琴子に、壮士は「だよな」ともう一度満足そうに頷いてみせた。
「だからわたくしは……あの、その時が来るまでお兄様と奈津とずっと一緒に居たい、です……。これでいいですかッ!?」
「うん、すごくいい」
壮士は今日一番の笑顔を浮かべつつサムズアップ。
その一言が聞きたいがために同居を渋っただけなのだ。
「琴子は可愛いなあ」
「もうっ! お兄様のいじわる! 心と穂乃佳様の気持ちがわかりましたっ」
恨み節を吐きながら顔を伏せ、こみ上げる羞恥に身体を震わせる琴子。
そんなレアな妹の姿を、目を糸にして愛でる兄と姉が居た。
「琴子」
「……なんですか?」
言うなれば、この一週間はアディショナルタイムのようなもの。
もう少しだけ。三人一緒に思い出を重ねる時間が残されている。
万感の思いを込めて壮士は言う。
「思い出いっぱい作ろうな」
「ふんっ、お兄様きらいっ」
琴子はしかし、拗ねた顔でそう言ってそっぽを向いたのだった。
◆◇◆
違和感。それが世界のすべてを満たしていた。
なにかがおかしい、と思い、壮士はその理由をすぐに知覚する。
身体がない。音がない。触覚がないのだ。
自分の息遣いも、拍動さえ感じ取ることができない。
直前まで何をしていたのかすら把握できないでいる。
なのに意識はある。己が何者であるのか理解できた。
そうして壮士は悟る。
これは夢だ。あの悪夢が今日も始まったのだ。
悟ったときにはもう手遅れだった。
実体のない全身を悪寒が駆け巡り、堪え難い嘔吐感がどこにも有りはしない胃を掻き乱す。
刹那、固着された視界の隅々にまで不穏な灰色が広がっていた。
――やめろ
壮士の願いは遠ざけられる。
声にならない声。逆らうことのできない肉体。身じろぎひとつできず、なにひとつ抗うこと叶わず、壮士は恐怖しながらその時を待つ。
やがて、灰色のなかにポツリとひとつ。
――クソッ! クソッ!
女だ。バケツをひっくり返したような血溜まりのなかで女が横たわっていた。
目袋が窪み、飛び出さんばかりに眼を剥く彼女は、口の端からよだれ混じりの血を流し、ごぼごぼと血泡を噴いていた。
愛らしかった顔立ちは血の気を失い、長い黒髪は凝固した血で汚れてしまって見る影もない。見るに堪えない姿にされた最愛の人が、声高に死を主張するようにガクガクと痙攣している。
せめて、口元だけでも拭ってあげたかったけれど、そんな僅かな慈悲すらも彼女に与えてやれなかった。
わかっている。
いつもそうだ。
――穂乃佳ッ! ほのかッ!
裸に剥かれ、ゴミのように打ち捨てられた無二の人。
誰にも看取られぬまま彼女の命の灯火が消えゆく様を、壮士はただ眺めることしかできない。
地獄以外のなにものでもなかった。
なにが理由でこうなったのか。誰に怒りを向ければよいのか。それらを考える精神的な余裕すらない。ただひたすらに地獄だ。
畳みかけるようにやってくるその悲惨な光景に、壮士は打ちのめされるように嘆きを叫び続けるしかできない。
ふと、きっともうなにも映っていない、空洞となった穂乃佳の目と目が合った。
――ソ、ジ……?
屍同然の彼女が助けを求めるようにこちらへ向けて手を持ち上げる。
壮士は嘆きながら手を伸ばした。どうか夢の中だけでも穂乃佳を助けさせてくれと、それだけを願って見えぬ手を必死に伸ばした。
だが、届いたと意識した瞬間、穂乃佳はひぃうと細く呼吸して、
――ウラギリモノ
「ああああぁぁぁ――ッ!!」
喉が潰れんばかりに絶叫して、壮士は滂沱と涙を流しながら自分の頭を抱えた。
数瞬我を失う時間を経て、壮士は早く短い呼吸を繰り返す。それから手指が自分の意思で動くのを確認し、全身に走る悪寒が引いてくれるのを辛抱強く待った。
そうしている内に、すぐ近くに人の気配があることに気づき、
「…………」
膝に手を置き、黒い美貌が憂いを宿した瞳で壮士を見つめていた。
壮士は確信にも似た予感を覚えながら問う。
「いま、何時だ」
「間もなく夜が明けます」
静かにそう答えて琴子は美しい所作で立ち上がると、迷いなくバルコニーへ向かった。
カーテンの端を握り、彼女は一度こちらを振り返ってから勢い良くそれを開け放つ。
まるで二人を覆う闇を切り裂かんばかりに。
つまりそういうことだ。
毎夜悪夢にうなされ、待ち焦がれた日がようやく訪れてくれたのだ。
「――さあ、お兄様。復讐しに参りましょう」
◆◇◆
決戦の朝。
「準備は?」
壮士は、ブーツの紐を締める琴子を一瞥しつつ、自身の装備の最終確認を行った。
二人が纏うは黒を基調としたサバイバルウェア。
この日を見据え、琴子が専用にあつらえた防刃仕様の戦闘服だ。
もっとも金属板などを用いた防刃ベストと違い、この繊維は刺突されると貫通してしまう。切れにくいというだけの物でしかなく、過度な期待は禁物だ。
「いつでも」
端的に答えた琴子は扱い慣れたナイフ二本と小型のリボルバー一丁を装備。そのほか予備の弾薬にスタンガン、催涙スプレーや医療キットと、いずれも小型かつ軽量な物を中心とした機動性を重視した構成となっている。無論これは体力の低い琴子の負担を下げるためだ。
「こっちも準備完了だ」
そのぶん壮士の装備はやや厚い。
相棒の自動拳銃と大ぶりのナイフを一緒に収めたホルスターを腰に巻き、その上から予備のマガジンや投擲武器の詰まったベルトポシェットを装着。インナーに高い防刃性を誇るベストを着込み、さらには携帯食や医療器具、簡易的なサバイバルキット等の入った小ぶりのクーリエバッグを背負う。
相談した結果、飲料はごく少量だけに留めることにした。水は環境を問わず重要な要素ではあるが、流石に何本ものペットボトルを持ち歩くわけにはいかないだろう。
何事においても見切りは必要だ。装備過多のせいで殺られた――なんてことにでもなれば目も当てられない。
と、そんな二人をまじまじと観察して、
「なんともまあ、金の匂いのする出で立ちですな」
皮肉っぽいセリフに反して心底感心したような悪魔の呟きに、琴子は即座に眼光を鋭くして、
「気分を害さぬよう一層配慮すると、そう約定したはずでは?」
「これは失言でした」
悪魔は一本取られたと言わんばかりに破顔しつつ一礼。
「お二人の入念なご準備ぶりを目の当たりにして、思わず漏れ出てしまいました」
「気持ちはわからんでもないけどな。俺もまさかこんな装備をすることになるとは思ってなかったし」
苦笑気味に言った壮士に、悪魔は「参謀様様ですな」と嗤ってみせ、
「元よりお二人には強く期待していたところですが、一層期待が膨らみます」
「貴方の期待など要りません――」
琴子はそこで一度言葉を切り、容赦のない暴虐を瞳に宿して言い放つ。
「神の手先は皆殺しにします」
「……是非」
刹那、琴子の威に気圧されたかの如く、悪魔が息を呑んだように見えなのはきっと見間違いではないだろう。
事実、白老は失態を誤魔化すように一つ咳払いすると、バルコニーを手の平で指し示し、
「それでは会場へご案内しましょう」
言った途端、一枚の扉が出現した。
飾り気のない木製に見える扉。しかしそれは日常と非日常を分かつ境界線だ。
それを壮士はジッと見つめ、それから悪魔に目をやり、
「少しだけ時間をくれないか。ほんの数分だけでいい」
「勿論です。野暮なことは申しません。奈津嬢と存分に話されると宜しい」
「悪いな」
「なんの。私は先に参りましょう。別れが済み次第その扉をお通りください」
悪魔は奈津に向けてニコリと微笑みかけてから姿を消した。
壮士と琴子は、示し合わせたように奈津に向き直る。
「…………」
二人が準備を始めた頃から奈津は一度も口を開いていない。
心配そうに胸の前で拳を握り、ただ二人を見守っているだけだった。
「えっと……」
「なんですか」
壮士のそれに、食い気味に言った奈津の声はやはり抑揚の無いもので、しかし憂う表情は少しも和らいでいなかった。
だから壮士は、
「まあ、なんだ……」
「だからなんですか」
情けなくも口ごもってしまう。
この時この場面、奈津へ贈る言葉がきっと誓いの一つになる筈だと、そう思ってきたのに。
「そんな顔するなよ」
「わたし、どんな顔していますか?」
「どんなって……」
こんな今にも泣き出しそうな顔を向けられては何もかも吹き飛んでしまう。
そのことが壮士は嬉しくもあり、同時に申し訳なかった。
「そうだな、見たことない綺麗な顔してる」
奈津にとって壮士は大切な妹を死地に誘った恨むべき男だ。
なのに彼女は、琴子だけでなく壮士のことも心から心配してくれている。
こんなに嬉しいことはない。
「壮君は嘘つきですね。綺麗な顔してるならいいじゃないですか」
「おお、ほんとだ」
ほんの少しだけ憂いを和らげてくれた奈津を目にしながら、壮士は掛けるべき言葉を練り上げる。
だが、いつまで経っても良案は浮かんでこなかった。
ならば仕方ない、
「最初に会った時に言質とったろう?」
「言質? ああ……」
普段通りのなっちゃんとの距離感でいいだろう。
それは四ヶ月の時を費やし、彼女と一緒に作り上げたモノだから。
「なにがあっても琴子は守る。必ずなっちゃんのとこに帰してみせるから」
「から?」
「頑張る俺になにか励ましの言葉をください」
「壮君はほしがりさんですね」
「そう言わずにどうか優しい言葉をひとつ。とびっきりの笑顔でもいいぞ?」
じゃあ、と奈津は暫く逡巡して、不意にこちらの首に腕を回した。
頬に触れる柔らかな感触――。壮士は大きく目を見開いて、
「こりゃ随分と奮発したな」
「気をつけて」
目の前。こちらの希望通りの綺麗な笑顔に、壮士は薄く微笑みながら顎を引いた。
暫く見つめ合った後、奈津は琴子に向き直ると、そっと妹の身体を抱き寄せて、
「危なくなったら壮君盾にして逃げるんだよ?」
「ふふっ、それはなかなか難しいお願いですね」
琴子はクスクスと笑いながらそう言って、奈津の背に腕を回す。
「だめ、約束して」
「わかりました。状況次第で前向きに検討します。それで許してもらえませんか?」
形のいい眉をハの字にして答える琴子。
奈津はしばし黙考し、「わかった」と抱擁を解くと、琴子の瞳を覗き込んで、
「駄目だって思ったらリタイアするんだよ?」
「それはゲームのルール次第ですから。許されるならそれも前向きに検討しましょう」
「お姉ちゃんとの約束だからね? ぜったいだよ?」
「はい、お姉様」
あと、と奈津に声をかけて、琴子は表情を妹から円成寺の当主のそれに変えた。
「一ヶ月待って私が戻らなければ、例の書類をお義父様と嘉斎《かさい》の叔父様にお届けするように。後のことはお二人が抜かりなく取り計らってくれます」
「畏まりました、お嬢様」
「貴女は円成寺を離れて構いません。個人的に綾部の叔父様と話したことがあります。身の振り方については叔父様とよくよく相談するように」
そこまで言って、琴子はもう一度柔らかに微笑み、それから自分の額を奈津の額にコツンと合わせ、
「こんなことに巻き込んでしまってごめんなさい。お姉様はこれまで十分尽くしてくれました。心より感謝しています。どうか幸せになってください」
「そんなお別れみたいなのいらない」
「……ですか。ならばさっさと神を殺して帰ってくるとしましょう」
ニコリと二人は微笑み合って、名残を惜しむようにもう一度抱き締めあった。
「んじゃまあ、そろそろ行くか」
ストレッチしつつ、軽い調子で壮士が言う。
一方の琴子は、首元でくすんだ輝きを放つ想い人の形見をぎゅっと握りしめて。
「ええ、参りましょう」
それを受け、ニヤリと笑ってノブに手を掛ける壮士。
琴子は不敵な笑みを貼り付けつつ、さっさと開けろと言わんばかりに顎をしゃくる。
「行ってくる」
「行ってきます」
奈津に告げたその言葉を最後に、二人の姿は扉の向こうに消えた。
◆◇◆
「いってらっしゃい……」
絞り出したその声を聞くべき人はどこにも居ない。
それでも奈津はその場に留まり、哀切の情を顔に貼り付けたまま消えた扉をながめ続けた。
そのまま一分が経ち、五分が経ち、やがて十分が経とうとしたその時――。
「なーっつん! あーそーぼー♪」
童女のようなその声が聞こえたと同時に、濃密な気配が部屋を満たした。
刹那、奈津は失望したように唇を噛んで、それからゆっくりと背後を振り返り、
「……寛人《ひろと》さんと葵依《あおい》さんは?」
「ひろとんもアオイもじゅんびかんりょー、なっつんのこと待ってるよ!」
「そうですか。なら案内してください」
「いいけど、お手紙とどけなくていいのー?」
「手紙……?」
「ほら、円成寺琴子に頼まれてたでしょ? 死んだら手紙とどけてーって」
「その件なら信頼できる人に任せてあります」
「ならあんしんだね! たぶんあいつ死ぬし」
瞬間、奈津は怒気を瞳に宿し神を睨みつけ、
「黙れッ……」
恫喝するような低い声。
しかし、
「やだー」
告げられた側に脅されたという意識は皆無だ。
「神様は神様なのでなっつんの言うことなんて聞かないのです」
「減らず口を……、悪魔はもう少し謙虚でしたよ?」
「ヘナチョコじーちゃと一緒にしないでー。神様はすーぱーごっどなんだよ?」
「なんでも構いません。早く二人のところに案内してください」
「いいけど。でもなっつん、ほんとーにゲームに参加するの? 死ぬかもしんないよ?」
「何をいまさら」
「だってさー。ひろとん、なっつんにスパイしてって頼んだけど、ゲームには来ちゃダメだって止めてたじゃん。神様も頼んでないし」
「私に裏切られるのを警戒してるんですか?」
「んーんー。べつに裏切ってくれてもいいのー。なっつんは円成寺琴子のおねーちゃんなんだし、そんなの関係なしにどうせ神様勝っちゃうから。ただ神様ってばなっつんのことけっこー好きだからね。ちゃんとちゅーこくしてあげなきゃと思って。おおっ、神様やっさしー」
「ふふ……、そうですか」
でも忠告なんて要りません、と奈津は嗤う。
「私にはゲームに参加する理由がありますから」
「そーなの? もしかしてひろとんたちのことどーじょーしちゃった?」
「いいえ、二人は関係ありません。個人的な理由です」
奈津にとって二人は命の恩人だ。もし神にさらわれたあの場所に寛人と葵依が居なければ、恐らく生きて帰ることはできなかっただろう。琴子と再会できたのも、こうして壮士を見送れたのも彼らのお陰だ。
故に寛人らの置かれた立場に同情しているし、心配だってしている。力にもなってあげたい。そうするだけの義理がある。
だが、結局のところ皆同じなのだ。壮士や琴子、寛人と葵依、そして奈津でさえ、皆が負った傷も不幸もすべてはこの邪神に端を発している。
「私はあなたを裏切りません。なっつんは神様の愉快な仲間ですよ?」
言いながら奈津は思う。
やはり琴子の推察は間違っていなかった。
「むぅ、調子いいこといってー。神様は醜い人間のいうことなんてしんよーしないんだからね! かんたんに騙せると思ったら大間違いなんだから! でも気になるから理由おせてー!」
神も悪魔も万能ではなく、そして彼らは、人という生き物に興味は示しても慮りはしない。
所詮は羽虫程度にしか考えていないのだ。
「なんですかそれ。ツンデレのつもりですか?」
「いいからー、り・ゆ・う! 個人的な理由ってのおせてー! なんでゲームに参加するのー?」
だって彼らは無知だ。
こちらのことを何も知らない。
「こう見えて私は神様に感謝しているんですよ? 正直諦めていましたから――」
綾部奈津がこれまでどう生きてきたのか。どんな想いでこの日を迎えたのか。
彼らは知りもしないし、興味すら持っていないのだ。
「あの女を生き返らせるわけにはいきません」
「? だれのことー?」
決まってるじゃないですか――、そう胡乱に呟き、奈津は血走った目を神に向けた。
「円成寺椿です」