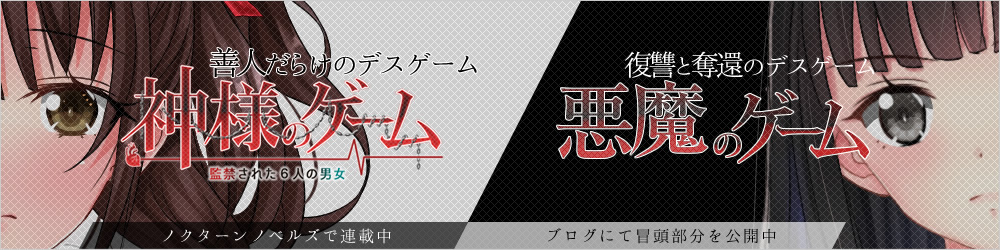円成寺の別荘から五分ほど歩いた森の中。
壮士はただ独りそこに立ち、自らの存在を周囲に溶け込ませてゆく。
「…………」
瞼を閉じてゆっくりと息を吸う。
鼻腔をくすぐる緑の匂い。
優しく頬を撫でる湿った潮風。
かすかに聞こえる野鳥の囀り。
それらを材料に、壮士は己の内で燻る熱へ語りかける。
もう少し待て。我慢しろと。
そうして心が凪いだ頃を見計らい、壮士は静かにホルスターへ手を伸ばした。
赤ん坊に触れるような優しい手付きで得物を取り出し、目線の高さに構える。
「手を密着。握りはハイグリップ。リコイルを受けないよう銃の中心線が手首を通るように……」
壮士はひとつひとつ口にしながら、ロバートに教わった構えを確かめてゆく。
理想的な姿を頭に描き、少しずつ現実の自分を重ねいく感覚。
「軽く前傾姿勢を取って体の重心は前に。両足は肩幅。右足を半歩後ろ、四十度外側へ開く……」
やがて理想に現実が追いついた頃、壮士は満足そうに一つ頷いて得物をホルスターへ戻した。
続けて二度・三度と同じ動作を繰り返えす。
日々百以上の数を重ね、ともすれば累計で万に届こうかという基本動作。
こうして愚直に同じことを繰り返していると、なんだか小さな頃を思い出す。
父親と兄に正拳突きの練習ばかりさせられていたあの頃。壮士はよく『こんな試合で役に立たないことばっか繰り返して意味あんのかよ』などと愚痴ったものだった。
「うん、あの頃は俺もガキだったな」
しかし年齢を、経験を重ねる度に思い知らされる。
基本は大事だ。やっててつまらないことこの上ないが、とても大切なことなのだ。
事実、
「ッ……」
壮士は今一度、今度は一段と速度を上げて得物を構えた。
イタリア製自動拳銃、ストライク・ワン。
――相性がいい物を選べ。
そんなロバートの勧めに従い、様々な銃を試し続けた末に出会った得物だ。
琴子同様、もう一人の相棒と呼んで相違ないそれは、もはや体の一部と錯覚するほど手に馴染んでいる。なので基本の反復練習は大切なのだ。
「よし」
相棒を腰に戻し、それから深呼吸をひとつ。
眼前に並ぶは人の形を模した木製の的。壮士はそれらを睨みつけ――、
「――ッ!」
破裂音が三発。頭、胸、腹と5メートル先の的を打ち抜き、続けて10メートル先の的に三発。
残弾を20メートル先の対象二体に浴びせかけ、横っ飛びに木の陰に身を伏せる。
空になったマガジンをリリースして次弾を装填。
反転しながらスライドを引き、今度は遮蔽物を盾に高い位置に設置された的を撃ち抜いてゆく。
そうして最後の一発の残響が消えた頃――、
「お見事です」
そんな平らな声と共に、ペチペチと緩い拍手の音。
「凄いですね。ぜんぶ当たってるんじゃないですか?」
言ってこちらに近寄ってくる奈津に対し、壮士は苦笑い気味に「どうも」と答えて、
「でもまあ、ぜんぶってことはないかな。遠くのと上の奴のは何発か外してると思う」
「十分じゃないですか。壮君は射撃が上手ですよね」
顎に手を添えて、ふむと頷きながら称賛してくれるなっちゃん。
一方の壮士はこみ上げてくるものを堪えるように口を押さえて、
「感無量だ」
「……なんです? やぶからぼうに」
「最初の頃と比べて今のデレようったら……、ちょっと感動してる」
眉をひそめる奈津に、ううっと泣きマネを返す壮士。
このクーデレさん。以前は事あるごとにココロをえぐりに来ていたし、こんな風に素直に褒めてくれることもなかった。いや、今でもえぐりに来るのはしょっちゅうなのだが。
それでも奈津の態度が随分と軟化したのは間違いない。
以前の彼女なら泣き真似をする壮士に対して「馬鹿じゃないですか」と一蹴していただろう。
デレてくれるのを待ち続けた身としては感動の一幕である。
「別にデレてなんか……」
「いいや、デレてる。俺がそう思うんだから間違いない」
「勘違いです。もう三ヶ月も一緒に暮らしてるんですよ? 多少は距離感も近くなりますよ」
そう、この日は奈津と出会ってから三ヶ月半。
壮士がグアムに滞在してから丸三ヶ月が過ぎようとしていた。
「距離感が? 近くなった? 俺と?」
「うっ……。顔ちか、ウッザ……」
食いつく壮士。頬を引きつらせながら後ずさるなっちゃん。
以前のそれと比べれば、ウザいなんてディスりさえ手ぬるく聞こえてしまうというものだ。
「それはそうと、なんだって朝っぱらからこんなとこまで。今日は一日オフだろう?」
「オフだからこんなところにまで壮君を探し来るハメになったんです」
「俺になんか用事?」
「用事もなにも今日は“兄妹の日”でしょう? あの子ずっと待ってますよ?」
「おっと、そうだった」
壮士はしまったとばかりに手を打って、慌てて片付けを始める。
兄妹の日とは、グアムに来て以来、だいたい十日に一度の頻度で開催される定例イベントだ。
もっともイベントとは名ばかりで、内容はこれといって決まっていなかったりする。
二人でドライブに出かけることもあれば、外で食事したり部屋でダラダラ過ごしたりと。ようはデートまがいに壮士と琴子が丸一日一緒に過ごす、ただそれだけの日だ。
この兄妹の日。もちろん言い出しっぺは琴子なのだが、彼女がこのイベントを望んでくれたことを壮士は心から喜んでいる。
琴子と過ごす時間が楽しい――なんてシンプルな理由はあるけれど、大切なのは兄妹の日の終わり方にある。
兄妹の日の最後はもれなくビデオレターを撮ることで締め括られる。
もちろんそのメッセージは将来記憶を奪われてしまう未来の琴子へ宛てたものだ。
嬉しかったこと、楽しかったこと、時には腹がたったことなど。琴子はその日の思い出を未来の自分へ語って聞かせるのだ。
『記憶』を『記録』に収める。その一役を担えることが、壮士は悲しくもあり、嬉しくもあり、誇らしくもあった。
壮士と琴子は並んでカメラの前に立つ。
どうにも照れくさくて壮士はほとんど口を開かないけれど、一生懸命話す琴子に寄り添って相槌を打つことだけは頑張っている。
自分も同じ気持ちなのだと伝える為に。
そうしていると魂を引き裂かれるような悲しみに襲われる。
どうにもしてやれない己の無力さ加減に吐き気を催す。
けれど、楽しそうに語る琴子の姿を眺める時間はとても幸せだった。
押し付けられた悲しみのぶんだけ。覚えた情けなさのぶんだけ。壮士は執念の糧としている。きっと琴子だってそうだろう。
この営みは、必ず勝ってみせる、取り戻してみせると魂に刻む儀式でもあるのだ。
ともあれ、片付けを終えた壮士は顎をしゃくり、
「行こうか」
「はい、行きましょう」
二人は並んで森の中を歩き始める。
こうしてただ歩いているだけでも奈津のちょっとした変化が伺えるというもので、
「やっぱ間違いないと思うんだけどなあ」
「まだその話してるんですか? わたしデレてません、ぜったい壮君の勘違いです」
呆れ気味にそう答える奈津との距離が、二ヶ月前と比べて半歩近いことを、果たして彼女は気づいているだろうか。
何にせよ、壮士にとっては喜ばしいことだ。
しかしそう思ったのも束の間。不意に奈津は顔を暗くして、
「あと二週間ほどで約束の四ヶ月、ですね……」
呟きのような奈津の言葉に、壮士は「早いもんだ」と軽い調子で答えたが――、
「……まだ悪魔さんから具体的な日程の知らせは来てないんですよね?」
「ああ、来てないよ」
奈津の表情は晴れないままだ。
きっと彼女は言外に『もしかしたら無い話になったんじゃ』と言っているのだろう。
約束の期限が近づくに連れて、奈津の憂いは現実的なものになってゆく。
その憂いが琴子だけじゃなく少しでも自分に向けられていれば、などと壮士は考えながら、
「でも、きっと近い内に来る。爺さん、ときどき顔を見せに来るし」
この三ヶ月のあいだ、悪魔は御機嫌伺いと称してときおり姿を現していた。
不定期かつその回数もほんの数回程度のことだ。
しかし老人との繋がりは今も確かに続いるのだし、元より悪魔は「最低四ヶ月」と口にしていた。
契約だって締結済みだ。現時点で日程の知らせが来ていないからといって、それで話が立ち消えになったとするのは無理があるだろう。
「…………」
「…………」
会話が途絶えた。
けれど壮士は、奈津と過ごす静かな時間も悪くないかと感じて、自ら進んで口を開かなかった。
掛けるべき言葉はあるのだろう。
心配しなくたって俺が琴子を守るから、だとか。
大丈夫だって五体満足で帰ってくるよ、だとか。
しかしどれも安っぽい。
似たようなセリフの数々を、壮士はこの三ヶ月間で何度も口にしてしまっていた。
だから事ここに至っては無駄に言葉を重ねることはせず、送り出してもらうその時に改めて、真心を込めた言葉を伝えられたらいいと思う。
きっとその時であれば、壮士にとっても、琴子にとっても、奈津へ送った言葉が誓いの一つとなるに違いない。
このさき絶望的な状況に追い込まれることがあるかもしれない。
あるいはもう死ぬしかないと、心が折れそうになる瞬間だってあるかもしれない。
しかし奈津に立てたその誓いが、歯を食いしばり立ち上がる理由になってくれる筈だと、そんな風に壮士は思うのだ。
「あ、思い出した」
と、奈津がパチンと手を打って、こちらの顔を覗き込んで来る。
「先週から聞こう聞こうと思っていたんですけど」
「なにを?」
「ほら、木曜日に届いたあの子ともうエッチしましたか?」
「…………」
もちろんオナホのことである。
ぜんぜん大切なことじゃないが、もう一度言おう。
奈津は『つるぺたサキュバス☆リリィ』にチンコ突っ込んだか尋ねているのだ。
「ねえねえ、壮君。どうでした? 前の子より良かったですか?」
「…………」
思い返すこと二ヶ月ほど前。壮士が毎日センズリしていると誤解を受けて以来、なっちゃんは時々オナホを買い与えてくれるようになった。
ふざけんなクソがと言いたい。
というか実際に言った。言ったついでに「誤解だ、もう買わなくていいから」と念押ししたのだ。
「リリィちゃんは使い込むほど覚醒するらしいんですけど……、もうクラスチェンジしちゃったのか、わたし気になってて」
なのにこの性悪娘は、嬉々と新製品を探してはア○ゾンでポチってゆく。
そして必ず壮士にレビューさせようとするのだ。
一度シャレで答えてやったことがある。
そしたらこのガキ『SOUKUN』という名前でア○ゾンにレビュー投下しやがった。
もっとも、その件については『どうか諸兄の助けとなってくれれば』と願っている壮士である。
ともあれ、ずっと年下の女の子にオナホを買い与えてもらっている24歳無職。
あまりの情けなさに死にたくなってくる。
(このガキ……)
壮士とていい加減理解している。
毎度毎度なっちゃんの軽口に付きあってはドツボにはまっている。
故に我慢だ。誘いに乗ってはいけない。
壮士は己にそう言い聞かせつつ、努めて素っ気なく言う。
「使ってない。箱に入ったまんまだ」
「そんな……、壮君ひどいです」
「なんにもひどくない。俺はいらんと何度も言った」
「だってエッチしてあげないどころか、封を開けてすらあげないなんて……、可哀想じゃないですか」
「あのな……、オナホを人扱いして、宛てがってやった娼婦みたく言うのやめろ」
「なんてことするんですか、壮君とエッチすることだけがあの子の生き甲斐なんですよ?」
「知ってるよ。オナホなんだから」
「リリィちゃんのことオナホ言わないでください」
「リリィちゃんはオナホだよッ! てかなんだよこの会話!」
瞬間ニヤリと嗤うなっちゃん。
そして敗北を悟る壮士である。
「クソがッ……、またツッコんじまった!」
「ホント、壮君ってからかい甲斐がありますね」
「そりゃなによりだ。楽しんでもらえてるなら本望だよ」
「もうオナホ飽きちゃいました?」
「いい加減オナホトークやめようぜ……」
「そうは言っても、結局あの時も行かなかったんでしょう?」
「あのとき? あ、ああアレな。うん……」
辛うじて平静を保つ壮士。
奈津の言うあの時とは、ロバートに誘われたアレを指しているのだろう。
確かにあの日、壮士は風俗に行かなかった。
しかしあの一件以降、ときどきその手の店に通うようになったとはとても言えない。
そんなこと言おうものなら、今でも大して高くないであろう評価が暴落するに違いないのだから。
そんな壮士の焦りを知る由もない奈津は、変化にとぼしい顔をやや暗くして、
「つまり、壮君は溜まっているのにオナホは使いたくないと、そういうことですね」
「いいからほっとけ。あと、女の子がそういう下世話なハナシするのは感心しないぞ?」
「私なりに壮君のこと心配してるんです」
へえへえありがとよ、とぞんざいに手を振る壮士。
気にかけてくれるのは有り難いことだ。
でもどうせ心配してくれるなら、シモのことより可愛い笑顔のひとつでも向けてくれた方がよほど嬉しく感じるだろう。
壮士は未だ、奈津が心の底から笑っている姿を見たことがなかったから。
しかし、そんなささやかな彼の願いが叶うことはない――。
「――なんなら私を抱きますか?」
壮士は無意識の内に歩みを止めた。
「…………」
気のせいだろうか。いいや、きっと気のせいに違いない。
いつもの軽口にしか聞こえない奈津のそれに、底知れぬ感情のうねりを感じたなんて、どう考えても気のせいだ。
壮士は眉間にシワを刻み、さながら妹を叱る兄のような声で言う。
「冗談でもそういうこと言うな。自分のことを大切にしろ」
「大切にって……、大げさですよ。ただエッチするだけのことじゃないですか」
奈津の答えはあまりに軽薄で、故に壮士はいくばくかの失望を覚えた。
別に壮士は聖人君子ではない。女に幻想を抱いてもいない。
彼女ぐらいの年頃の子が多少性に奔放であっても『そういうものか』ぐらいにしか思わない男だ。
しかしそれも人に拠る。
余計なお世話なのは重々承知しているが、奈津がそういう価値観でいたという事実が悲しかった。
そんなこちらの気持ちを見透かしたように奈津が言う。
「壮君って、私にヘンな幻想抱いていませんか?」
「幻想って?」
「わたし、ヴァージンじゃないです。経験あります」
明け透けな奈津の告白を受け、壮士は目を見張って驚きをあらわにした。
それを聞いたところで特段なにということはない。ないが、こんなにも長い期間を一緒に暮らしてきたなかで、奈津に男の気配を感じたことがただの一度もなかったのだ。
「というかヤリまくりです」
「へ、へぇ……、かなり意外だ。彼氏いたんだ」
「彼氏なんていません」
「ああ、悪い。変なこと言ったか……?」
「それも違います。別れたとかそういうのじゃないです」
彼氏はいない。別れたとかでもない。でもヤリまくり。
さっぱり意味が分からない。
「はっ!? ま、まさか……お前、琴子と……」
「壮君は馬鹿なんですか?」
「だよな……。ビックリしたぁ……」
「私がビックリですよ……」
「それで、あの、ヤリまくりってのは……」
「冗談です」
「? えっと、それはどういう……」
「だから冗談です。ぜんぶ軽口です。なっちゃんは処女です」
「…………」
「私の裸想像しました? というかオッキしちゃいました?」
「ま、またもてあそばれたッ!」
「もてあそんでやりました」
「ちょっとデレたと思ったらこれだ!」
「だから……、デレてないですって」
ため息混じりにそう言って、奈津はこちらを置き去りに森を進む。
壮士は小気味よく歩いていく奈津の背を暫し見つめ、それから「置いてくな」と後を追った。
故に壮士は気づけなかった。
「なっちゃんはヤリまくりなんですよ、そうくん……」
口のなかでそう呟いた奈津が溢れそうになる涙を必死に堪えていたことに――。
壮士は気づけなかったのだ。
◆◇◆
「待ちくたびれました」
言って、腕組みしながらプーっと頬をふくらませる琴子。
純白のワンピースを纏う彼女は、まさに深窓の令嬢然とした出で立ちで。
「すまんすまん」
「まったくお休みの日まで射撃の練習とは……、お兄様は戦闘狂ですか」
物凄く可愛いけれど、正直琴子のイメージじゃない、なんて考えつつ壮士は苦笑い。
「今日が最後の兄妹の日となるやもしれません」
ああ、と頷きを返す壮士。
約束の日は近い。彼女らと平和に過ごせる機会はそう多くないだろう。
「お手を」
「喜んで」
壮士は差し出された手をそっと握る。
相も変わらずもやしのような細く白い腕。
果たしてこの手が再び一馬の、心の手を握る日が来るだろうか。
「行こうか」
「はい、お兄様」
来るのを待つのは性に合わない。
彼女の細い腕と、壮士の太い腕で掴み取るのだ。
最後の“兄妹の日”が始まった。