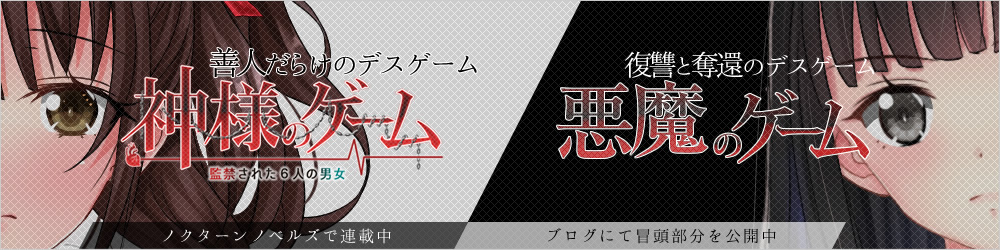グアムに着いた翌日の早朝。
奈津に用意してもらったトレーニングウェアに身を包み、壮士はランニングに向かった。
まさかグアムを走ることになるとは想像すらしていなかったが、元より休職した後に取り組もうと考えていたことだ。
悪魔のゲームがどんなものであれ、体力があって困ることはないだろうし、その辺りが生死の明暗を分けるとも限らない。
パートナーの背は低く、身体は小さく、二の腕だってもやしのように細い。琴子はとても聡明な女の子だが、体力面ではあまり期待できないだろう。
彼女の分まで壮士が動き、いざという時には盾とならねばならない。その為のトレーニングだ。
もともと、壮士は体を鍛えるのが好きな方だ。
物心がつく前から空手を叩き込まれていた兼ね合いで、体を動かすことは苦ではない。もっとも、その契機となったのは『運動のできるガキはもてる』という不純なものなのだが。
学年で上位数名に入るほど足が速く、球技もそこそこできた壮士は、お陰様で小中学の頃は結構もてた。そのつど穂乃佳から文句を言われたことなんかも、今となっては良い思い出だ。
「はっ、はっ、はっ……」
そんな取り留めのないことを考えつつ、一定のリズムを刻み、呼吸を整え、異国の道路を進む。
社会人になってから運動する機会がめっきり減ったせいだろう。ものの3キロほど走っただけなのにやたら苦しい。胸が痛い。足を止めたくなる。
けれど、ランニングはいいものだ。
プラス3キロを越えたあたりで苦しさが消え、いくらでも走れそうな気になってきた。
全身の隅々にまで充足感が行き渡り、頭の中が真っ白に塗りつぶされてゆく。
辛いことや悲しいことの一切が煙のように消え、愚直に前へ進むことだけが己の使命であるかのように錯覚する。
現実逃避しつつ、現実に向き合う為に体を鍛えられるのだから、まさに一挙両得。やはりランニングはいいものだ。
そうしておおよそ10キロに及ぶランニングを終えて、壮士は円成寺の別荘に戻る。
「おかえりなさい、壮君」
待っていてくれたのか、入り口にはタオルとスポーツドリンクを持った奈津が立っていて、
「すごい汗ですね。初日から飛ばしすぎじゃないですか?」
「はぁ……、はぁ……、だな、ちょっとやりすぎたっ……」
言って、奈津から受け取ったタオルで顔を拭きながら、壮士は息を整える。
ブランク明けに10キロはやり過ぎだったと今では思うが、知らぬ内に気負っていたのかもしれない。長く現実逃避していたかったから、なんて情けない理由じゃないと思いたい。
「朝食の準備ができています。着替えてきてください」
「ありがとう、琴子は?」
実のところ、壮士はグアムに来てからまだ琴子と会えていなかった。
奈津との観光を終え、この別荘にたどり着いた頃には、琴子は出かけてしまっていたようで、
「お嬢様なら昨晩の内にお戻りですよ」
「そうだったんだ。帰ってきてたんなら、声掛けてくれたら良かったのに」
「私もそう言ったんですけど……、心の準備がしたいと仰るものですから」
「心の準備……? 俺と会うのに?」
壮士が首をひねってそう言うと、奈津は処置なしとでも言わんばかりに肩をすくめ、それから「まあ、会えばわかります」と答えて、
「お嬢様がリビングでお待ちです。早く着替えてきてください」
それから暫く。
「うわ……」
「あの、そんなにまじまじと見ないでください……」
自称妹との邂逅を果たした壮士は大きく目を見張って固まった。
これが驚かずにいられようか、
「どうでしょうか……?」
恥ずかしそうに頬を紅くする琴子の、あの美しくも長い黒髪が失われてしまっているのだから。
顎のラインで整えられたショートヘアーは、以前の和風然としたそれと打って変わり、毛先の動きを出した現代的な髪型だ。
ともあれ、それを目にした壮士が最初に発した言葉は、
「めちゃくちゃ可愛いな!」
「あ……、ありがとうございますっ!」
似合っているか不安だったのだろう。
琴子は安堵の滲む吐息を溢して、それから笑顏と共にふわりと短い黒髪を揺らした。
まず褒めるところから入るあたり、さすが壮士は、美月に“女ったらし”の称号を受けた一馬の弟である。もっとも、多少の計算を含んでいるであろう一馬のそれと違い、壮士はただ感じたままを口にしただけだ。
馴染み深い長髪はその堅苦しい口調と合わさり、言わば琴子のトレードマークのようなモノだったが、ショートヘアーになった姿は愛らしさがグッと増して、良い意味でイメージチェンジできていると思う。
「凄く似合ってて可愛いけどさ。なんで切っちゃったんだ? もったいない」
「ふふっ、それはですねぇ~」
壮士の率直な感想がよほど嬉しかったのか、琴子はニマニマとだらしのない笑みを浮かべつつ、もったいつけるような声で言う。
「髪を掴まれて殺されないためですっ」
「あ、うん。そういうことか……」
お返しのような琴子の率直な理由を受け、頬を引きつらせながら食卓につく壮士。
表情とセリフとのコントラストが酷い事になってしまっている。
が、琴子の言うのは至極もっともで、あの掴みやすそうな長い髪は荒事に於いて弱点となるに違いない。実に彼女らしいシビアな考え方だ。
「ときにお兄様?」
「うん?」
「褒めていただいたのはとても嬉しいのですが、一馬様は……、あの……」
言葉をしりすぼみさせて、失われた髪を惜しむかのように短い髪を撫でつける琴子。
そんな自信なさげな態度を見せられては、さしもの壮士もピンとくる。
「兄貴がどう思うかって?」
「はい……」
「そりゃ心配しすぎじゃないか? 兄貴なら間違いなく可愛いって言うぞ」
「もちろん私とてそう思っています。ただ……、心や百合子様も髪が長いでしょう? 髪の長い女の方がお好みなのではないかと心配なのです……」
「う、う~ん……。やっぱ気にしすぎっていうか、そうじゃないっていうか」
琴子の懸念を受け、『さすが恋愛初心者』と思わずにいられない壮士だ。
なんというか、琴子の心配は根本的にズレている。
確かに心や百合子は髪が長い。百合子の名前を挙げたのは、一馬が分かりやすく好意を示した唯一の人だからだろう。
しかし、一馬の好みをどうのこうの言うのなら――、
「えっと、兄貴の元カノってどうだったかな?」
「もとかの……?」
過去、一馬が付き合ってきた女性から探るのが常道だ。
一馬にすれば心なんてハナっから恋愛対象外だし、最終的に一人の女として愛したのだとしても、それは外見云々の話ではない。百合子も然りで、あの環境下でこそ覚えた親愛だろう。
だから、単に一馬の外見的な好みを知りたいだけなら女性遍歴と照らし合わせるのが正解なのだ。
「ああ、そうだった。確か初めて付き合った子は――」
「もう結構です」
こちらの言葉を遮り、琴子は右手を突き出してノーサンキューのサイン。
真顔かつ真一文字に結ばれた唇から、なんとなく不快感のような感情が伝わってこなくもない。
「いやだから、兄貴が……」
「聞きたくありません」
意外なことにこの腹黒さん。嫉妬深く、女性関係に不寛容な質《たち》なのかもしれない。
「いいのか?」
「いいのです」
反面、心や百合子のことなんて全然ウェルカムな感じなのだから、琴子のなかのOK・NGラインがどこで引かれているのかサッパリ分からない。
あの場にいた女性達以外と関係を持つのは許さないとか、そういう感じだろうか。だとしたら、生き返った一馬は結構な苦労をさせられるだろう。
そんな微妙な心持ちになっていた壮士の内心など知る由もない琴子は、空気を変えるように小さく咳払いして、
「それはともかく、昨晩は申し訳ありませんでした。せっかくお兄様が来てくださったのに」
「ぜんぜん気にしてないよ。髪を切りに行ってたのか?」
「いいえ、髪は何日か前に日本で。昨日は人を迎えに出かけていました」
迎えと言う言葉に、壮士は少しだけ違和感を覚えた。
いま現在この場に居るのは琴子と壮士、奈津の三人だけではない。琴子の身の回りの世話をするであろう女性や、警護や運転手を務めるであろう男性等、数名の人がこの別荘に滞在している。琴子がいかに庶民と異なる存在なのか、この一点だけでも伺えるというものだ。
その琴子が人をやるのではなく自ら足を運んだというのだから、迎えに行ったその人とやらは相応の立場にある人ということだろうか。
そんな壮士の覚えた疑問に気づいてか、琴子が説明を重ねる。
「私達にとって師となられる方ですから。私自身がお迎えせねば礼に失します」
「お師匠さん?」
「はい、実は髪のこともその方にアドバイスしていただいたのですよ」
「……なるほどな」
概ね琴子の言うところの『人を殺す練習』が見えてきた。
銃器が扱えるロケーション、それを師事する人のアサイン。悪魔との交渉を行いながら、琴子はその二つを用意する段取りをしていたに違いない。
「ということは、やっぱなっちゃんの凄腕殺し屋説は否定されたか」
「バカじゃないですか?」
小気味よく飛んできた奈津のツッコミはいつぞやと全く同じもので。
それを見ていた琴子が嬉しそうに微笑みながら言う。
「良うございました」
「なにが」
「随分と奈津と打ち解けられたようですね」
「そう見えるか?」
「見えますとも。言ったでしょう? お兄様ならきっと大丈夫ですよと」
「なっちゃん、なっちゃん、俺ら仲良しに見えるってよ」
食器を並べていた奈津はいかにも面倒といった感じに小さく溜息をついて、
「知りません」
素っ気なく答えた奈津の表情はもちろん真っ平らで、声のトーンからも感情の一切が覗《うかが》えない。
ランニングの帰りを待っていてくれたあたり、いくらか距離を縮められた気がしないでもない壮士だが、残念なことに、なっちゃんのそれが初対面の時と何が違うのか皆目理解できなかった。
「琴子」
「はい」
「本当に打ち解けたように見える?」
「ええ、見えます。その内お兄様も分かるようになりますよ」
そう言って、琴子はクスクスと笑ったのだった。
◆◇◆
朝食を終えた壮士は、散歩がてらにと琴子に誘われ別荘を案内してもらった。
琴子の説明によると、海岸線に面した別荘の周囲一帯が円成寺の私有地だそうで、建物の反対側にある林の中に射撃練習が行える設備や、アスレチックなどの各種トレーニングが行える設備を整えてあるとのことだ。
興味本位で壮士が『どの辺までが円成寺の土地なんだ』と尋ねると、
『私も正確には把握していませんが、あそこからあの辺りまででしょうか』
と、なんともアバウトな答えが返ってくる始末。よくもまあこんな小さな島にこれだけ広大な土地を所有したものだと、壮士はただただ圧倒されるばかりだった。
そうして壮士、琴子、奈津の三人が最後に訪れた砂浜で彼は待っていた。
「初めましてキリヤマソージ君。ロバート・マイヤーズだ」
流暢な日本語でそう言って、快活な笑みと共に手を差し出してくるスキンヘッドの黒人男性。
この壮年が琴子の言うところの師となる人であり、彼女が迎えにいった人であろう。
概ね歳の頃は三十代半ばといったところだろうか。もっとも、外国人ということもあって今ひとつ自信が持てない。
180センチを超えるであろう身長は、米国人としては然程珍しくないのかもしれないが、170センチそこそこの壮士の目にはかなり威圧的に映ってしまう。
海外デビューしたての壮士は、いくらか物怖じしつつも差し出された手を握り返して、
「初めましてマイヤーズさん。桐山壮士です」
「ああ、よろしくソージ。俺のことはロブと呼んでくれ」
手を握った瞬間、壮士は長く武道をたしなんできた経験から、この男性が強者であることを朧気に察した。
映画の登場人物達のような派手な見た目は有していないが、ロバートの肉体は均整の取れた筋肉に覆われており、それが一長一短で身につくような類の物でないことは一目見て分かった。
「じゃあ遠慮なく。ロブと呼ばせてもらいます。日本語お上手ですね」
「長いこと岩国に配属されていたからな。上手いだろう?」
「ということは、軍人さんですか?」
「元・軍人だな」
言って、ロバートは軽く口の端を持ち上げながら琴子に目配せする。
「ロブは二年間アメリカ陸軍に所属ののち海兵隊に志願され、海兵時代に実戦を経験されています。帰任後はサンディエゴで教導の任に就かれていました」
「で、今は色々あって、グアムで観光客相手に射撃練習場を営んでる一般市民という感じだな」
琴子の説明を引き継ぎ、ロバートが苦笑いしたところで自己紹介が終わる。
実戦経験アリ。そのプロフィールに壮士は軽く目を見張りながらロバートへ目を向けて、
「あの、初対面でこんなこと聞くのは失礼だと分かっているんですが、差し支えなければ教えてください」
「堅苦しいな、遠慮せずになんでも聞いてくれ」
朗らかな笑顔を浮かべて、ロバートは大仰に手を広げてみせる。
そんな彼に対して壮士はコクリと一度喉を鳴らして問うた。
「何人、殺しましたか?」
失礼極まりない質問だと思う。ともすれば、この人の古傷を抉るような愚行かもしれない。
けれど、今の壮士にとっては何よりも大切な事だ。壮士は今、人を殺す術を学ぶ為にこの場に立っているのだから。
こちらの予想に反して、ロバートは表情ひとつ変えずに淡々と告げる。
「初めて人を殺してから三日後に五人殺した」
「…………」
「そこからは数えるのをやめたよ」
「ありがとうございます。変なこと聞いてすみませんでした」
壮士は自責に顔を歪め、精一杯の謝意を込めて腰を折る。と、下げた頭の上から柔らかな吐息が漏れる音が聞こえて、
「君は真面目だな、悪いヤツじゃなさそうだ」
「そうでもないですよ」
壮士は低い声でそう告げて、ゆっくりと頭を上げた。
過酷な経験を積んでいるであろうロバートに言うのはおこがましい限りだが、壮士は彼に人殺しを師事しようとしている。見ず知らずの他人を効率良く殺す為に、だ。
そんな男が悪い奴じゃないわけがない、悪い奴なのだ。
「まあ、ソージが悪いヤツかどうかは時間を掛けて知っていこうじゃないか」
どっちでもいいけどな、とロバートは不敵に笑い、それから数歩後ろへ下がった。こちらとの距離は目算で三メートルほどだろうか。
どっちでもいいという言葉に、壮士は内心同意しながらも、彼の取った行動の意図が分からず眉をひそめる――が、答えは直ぐに出た。
ロバートはニヤニヤと嗤ったまま、手の平を持ち上げて四本の指をクイクイと手前に引き、
「挨拶代わりにちょっと見てやるよ」
「…………ッ」
瞬間、壮士は足の裏で砂を巻き上げ、滑るように壮年との距離を詰めた。
置き去りにされた「上等だ」という言葉が聞こえたのは、その懐に深く入り込んだ後。壮士の見せた反応は、挑発した側が不意打ちと錯覚して然るべきほどに早い。
軽く腕を持ち上げただけだったロバートは、黒髪の青年の思い切りの良さに一瞬だけ虚を突かれたように固まったが、直ぐに身を低くして迎え撃つ。
「ら……ッ!」
黒い瞳に好戦の色を浮かべて、壮士は左の拳を顎めがけて突き入れる。風の音が鳴るような鋭い一撃は、大の男の意識を刈り取るだけの威力があった。
その直後、
「いいね」
口笛を鳴らし、ロバートは壮士の拳を軽く叩いてパディングする。が、壮士にとってそれは見せ弾だ。身体を内側に泳がされる形となった壮士は、その勢いのまま腰をひねり渾身のローをロバートの太腿へ叩き込む――、
「――――っ!」
右足がめり込もうとした刹那、眼前に映るロバートの姿が一回り大きくなった。密着され威力を殺された打撃は有効打とならないばかりか、身を投げ出すように身体を預けられ、壮士は為す術なくロバートを抱きかかえるように後ろへ倒れ込んだ。
圧し掛かる巨躯の重圧に、壮士は肺から空気を吐き出しながら、
「まだっ!」
マウントだけは取らせはしまい。壮士はロバートの胴に脚を絡めながら左腕の関節を決めるべく腕を伸ばした。
まだ終わっていない。得意とする立ち技で打倒できなくとも、ちょっとしたことで優劣は裏返る。この程度の劣勢など幾度となく経験してきた。
「終わりだ」
直後、そんな己の考えがいかに浅はかさだったのか思い知らされた。
首筋に感じる冷たい鉄の感触。目に見えずとも分かる。押し当てられているのはナイフだ。
耳障りなほど心臓が早鐘を打ち、嫌な汗が全身から吹き出てくる。
実際にロバートがこちらの喉笛を掻き切ることはない。そんなことは分かりきっているのに――、
「ンクっ……、っ……」
首に刃物を押し当てられた経験など一度もない。まるで制御の利かない恐怖心が無尽蔵に溢れ出てくる。
命が奪われる現実を突きつけられ、壮士は息を乱し、指の一本すら動かせなかった。
「そんな緊張するなって。ホラ、刃は落としてあるだろう?」
ポンポンと慰めるように肩を叩き、ロバートは壮士の眼前にナイフを掲げて見せる。
人懐っこい彼の笑顔を目にして、ようやく壮士は肩の力を抜いて、
「ナイフは反則じゃ……ないか」
反則も糞もあろう筈がない。これは試合ではなく手合わせですらなく、純然たる殺し合いだ。
ロバートはこちらを殺すという選択肢を持って臨み、壮士はそれを持たないまま対峙した。
実際に殺るか殺らないかは別の話だ。
殺されるかもと意識していれば安易に懐へ飛び込めなかった。腰の裏に隠されていたであろうナイフにも警戒心が働いたかもしれない。砂を蹴り上げ、握り込むことなどの卑怯な手を取ることができたし、尻尾を巻いて逃げることすらできた。
要するにロバートと壮士との間では前提条件が隔絶していたのだ。
「ソージ」
「はい」
「予想以上に好戦的だったのが少し気掛かりだが……、まあ、そこは気にしないでいい。ビビって身体が動かなくなるヤツよりよっぽどいいからな」
ロバートのそれは、差し引きすれば褒めてくれているのだろうが、壮士としては素直に喜べない。注意深く観察し、出方を窺っていれば別の展開もあったかもしれないのだから。
以前に悪魔からも似たようなことを言われている。改善すべき悪癖だ。
「でもな、ソージ。一番大事なことは“殺すこと”じゃなくて“殺されないこと”だ。
コトコには殺す方法をトレーニングしてくれってオーダーを受けているが、そんなもんはオマケだ。まずは生き残れ。身を守る方法を身に付けろ。死んじまったらそこでオシマイだ。コトコを守れなくなるし、リベンジもできない。それで良けりゃ教えてやる」
馬乗りになったまま「どうだ?」と笑うロバートに、壮士は諦念を込めた溜息をつき、
「是非お願いしたいんですが、ロブは教導にいたんでしょ? ってことはアレだ。有名な軍曹殿のようなトレーニングなんですよね?」
「なんだ、ソージは海兵隊《マリーン》式がいいのか? 俺はそれでも構わんぞ?」
「いえっ、ウジ虫とかクソとかは勘弁していただきたいですっ、軍曹殿!」
「俺は軍曹じゃない、元・曹長だ」
「うわ……、曹長ってたしか下士官最高位だったような。叩き上げの鬼だ……」
言った直後、奈津が「階級知ってるとか、壮君軍オタ……」と呟いたが気にしない。
男子の多くは軍隊とか武器とか好きなのだ。だいたいからして、この程度の知識で軍オタ扱いされては本物の軍オタさんに失礼だ。
ともあれ、壮士は改めて目の前の壮年に目を向ける。
悪魔のゲームが始まるまで後たったの四ヶ月弱。どこまで、あるいはどれだけ身につけられるか分からない。ナイフを押し当てられ恐怖した自分に失望だってしている。
けれど、大切な人を取り戻す為の、大切な義妹を守る助けとなるならいかなる艱難辛苦に耐えてみせよう。
壮士はシッカリとロバートの瞳を見据えて手を差し出す。
「宜しくご指導下さい。お師匠様」
「うむ、苦しゅうないぞ、若造よ」
「苦しゅうないって……。アンタ、本当にアメリカ人かよ」
こうして、壮士と琴子の『人を殺す練習』は始まりを告げたのだ。