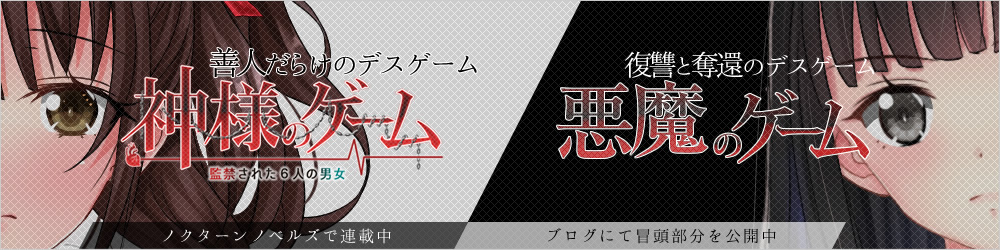Introduction
「なあ、自称妹よ」
「なんでしょう、お兄様。あと自称ではありません。確定している未来です」
「確定してるんだ」
「ええ、私が正妻で心が第二夫人。つまり私は紛うことなきお兄様の義妹です」
「第二って……、そんなのアイツが納得するかよ」
「心は元から桐山なのですよ? 婚姻関係は私に譲ってもらいます」
「譲るもなにも兄貴はあれで常識人だし、二人ともってのは無理じゃないかな」
「一馬様ご自身が二人に愛を告げたのです。責任は取っていただかないと」
「まあ兄貴が納得? したとして、心は絶対ゴネるだろうな」
「ヤです。私は桐山性になりたいのですっ」
「ヤです、とか言われても」
「ヤですっ」
「まあいいや。俺の知ったこっちゃない」
「良くありません。然るべき時には私の味方をしてください」
「そんな機会が来れば、前向きに検討しようじゃないか」
「必ず来ます。愛の力は偉大ですからね」
「そうかよ」
「そうですとも」
「で、愛情深い妹様はこんな展開予想していたか?」
「いいえ、私も驚いています」
「…………」
「…………」
「あのさ」
「はい」
「ぜんぜん驚いているように見えないんだけど?」
「でしょうね、想定内ですし」
「…………」
「…………」
「え? なんで嘘つくんだよ」
「私のアイデンティティだからです」
「また訳わかんねえことを……。なんで小さな嘘を挟むかな」
「ふふ、そのセリフ、心と同じです」
「そりゃあ心だって言うだろうさ、腹黒な我が妹よ」
「そういう私を一馬様は好いておられるのですよ、敬愛するお兄様」
「…………」
「…………」
「ようやく、だな」
「はい、この時をどれだけ待ち焦がれたことか」
「殺るか」
「殺りましょう」
…………
……
「俺はそんな気がしないんだが、あんたにとっては初めましてか」
「私の場合は、お久しぶりです、とでも申せば良いのでしょうか」
「まずは自己紹介といこう」
「改めて自己紹介しましょう」
「俺の名前は桐山壮士」
「私の名前は円成寺琴子」
「榊穂乃佳の婚約者で、桐山一馬の弟。あと、悪魔の“手先”だ」
「桐山心の無二の友で、桐山一馬様を愛する女。悪魔の“契約者”です」
「…………」
「…………」
「いや、そこは手先で合わせとけよ……」
「お兄様こそ、アレの手先に堕ちるなんて情けないっ」
「ん? ああ、こっちの話だ、気にしないでくれ」
「ただの兄妹の睦み合いです。お気になさらず」
「さて、挨拶も済んだことだし、さっそく始めようか」
「さっさと始めてしまいましょう」
「わかっているとは思うけど」
「ご理解されているとは存じますが」
「俺が死ぬか、あんたが死ぬか」
「私が死ぬか、あなたが死ぬか」
「それ以外の決着はない」
「それ以外の決着はありません」
「――さあ、殺し合おう」
「――さあ、化かし合いましょう」
悪魔の章 プロローグ
「殺人に必要なものとはなんだと思いますか」
悪魔との契約を終えたあと、円成寺琴子《えんじょうじことこ》が最初に口にしたのはそんな質問だった。
桐山壮士《きりやまそうじ》に殺人の経験はない。
当然だ。壮士は現代日本で生まれ育った普通の人なのだから。
もっとも壮士は、実家が空手道場を営んでいる関係で人を殴ったり蹴飛ばすことには慣れている。
父親や兄は血の気が多く、その二人と同じ血が流れている壮士とて口より先に手が出るタイプだ。
親子、ないし兄弟喧嘩が発生した際には、もれなく暴力沙汰へと発展する。
そういう意味で壮士が修めている空手は競技レベルを越えた実戦に近いものと言えよう。
だからといって相手を殺しに掛かったことなど、ただの一度もない。
殺すどころか、武道の危険性をその身で以って理解しているが故に、どれだけ頭に血が上ろうとも必ずストッパーが働く。
それはもう本能といって相違ない。
意識せずとも一線を越えてしまわぬよう身体が勝手に加減するのだ。
だから壮士は彼女の質問にこう答えた。
殺人に必要なものとは“覚悟”だ、と。
答えを聞いた琴子は満足そうに顎を引いて、
「まったくもってその通りかと存じます。差し出がましくも実体験として申し上げると、現実の殺人は頭で想像するよりもずっと困難です。生半可な覚悟では成せません」
きっと彼女はこちらの覚悟を確かめたかったのだろう。本当にお前は殺れるのか、と。
あるいは先達としてアドバイスしてくれたのかもしれない。躊躇ってはいけない、と。
悪魔のゲーム。
神と悪魔に成り代わり、人間同士が殺し合う代理戦争。
壮士は悪魔の側に立って事に臨む。
悪魔の側が存在するということは即ち、神の側に立つ人間も存在するということだ。
殺るか殺られるか。このゲームは比喩ではない本当の殺し合いだ。
壮士が成すべきは神殺しであって人殺しではない。
しかし、そこへ至るまでの経過で殺人は避けて通れないだろう。
壮士は、神様のゲームという邪神の気まぐれで兄と従妹と婚約者を同時に失った。
あの忌まわしきゲームが終わって約一ヶ月。この一ヶ月は文字通りの地獄だった。
甚大な喪失感にどれほど苦しんだか。あまりの無念にどれほどのたうち回ったか。
それでもいざ人を殺さねばならなくなったとき、躊躇うかもしれない。
いざ自分が殺されるとなったとき、怯えるかもしれない。
そんな予感を覚えていないかといえば嘘になる。想像と現実は違うのだから。
けれど、兄と約束したあの瞬間から壮士の腹は決まっている。
あらゆるものを代償とする覚悟があった。
いいや、違う。壮士はこの機会を得る為に既に三人もの肉親を生贄に捧げている。
だからこそ、何としても勝たねばならない。これはすべてを取り戻す戦いなのだ。
この思いを唯一共感してもらえるであろう琴子はしかし、
「けれど否です、壮士様。人を殺すのに必要なものは覚悟ではありません」
じゃあなんだと壮士は問うた。
神が憎い。殺す。神に与《くみ》する者も同類だ。その覚悟以外に何が必要だというのだ。
琴子は口元を緩めて答える。
「念の為に申し上げておきますと、私は貴方様のお覚悟を疑ってなどいません。このゲームに敗北すれば壮士様は殺されるのですから」
厳密には違う。壮士が老人と交わした契約は役務を負うこと。つまり神殺しを目的に、悪魔のゲームに参加することそのものが壮士の負う義務となっている。
しかしながら、このゲームは殺し合いだ。敗北イコール死となる可能性が極めて高い。そういう意味で琴子は『負ければ殺される』と表現したのだろう。
それに、先ほど彼女と交わした“約束”のこともある。たとえ途中下車が許されるのだとしても降りるつもりなど毛頭ない。
でなければ穂乃佳や心を取り戻せないばかりか、一馬が無駄死にとなってしまう。壮士はどんな手段を使ってでも神を殺さねばならないのだ。
「故に覚悟などあって当然至極。私がお尋ねした必要なものとは、もっと現実的なものです」
言って、かすかに首を傾けながら微笑みかけてくる琴子。
その笑顔は年相応に愛らしく、なのに黒水晶のような瞳は氷のように冷たくて。
「殺人に必要なもの、それは知識と技能であると私は考えます。事に臨むにあたり、私たちは効率的に人を殺す術《すべ》を、あるいは生き延びる術を身につけなければなりません。
どの部位をどの程度傷つければ、肉体がどんな機能不全を起こすのか。人体の構造、急所の位置、体術、銃器刃物の扱い、拘束法、応急処置を始めとする医療知識、サバイバルに関する教養も必要かもしれません。それらを学び、実践するに叶う技能を習得すべきと愚考します」
スラスラと所見を述べる琴子に、壮士は目を見張ることしかできず。
琴子はしかし固まるこちらに構うことなく、優しい微笑みを貼り付けたまま続ける。
「このゲーム、勝たねばなりません。そして私たちは必ず勝ちます」
確固たる決意。揺るぎない自信。削ぎ落とされた価値観。
「勝つために必要なことはすべてやります。勝利とは、おのが才覚と努力でもぎ取る物なのです」
琴子のそれは聞き覚えのある言葉だ。
たしか彼女の母親が同じようなことを言っていたと思う。
琴子はかのゲームを通じて情けを学び、愛を知り、そして最後にすべてを失った。
ただ眺めることしかできず、実際に彼女と触れ合ってこなかった壮士でも分かる。神様のゲームを生き残った琴子は大きく変わった。
椿が望んだ通りに太く強く成長したと思う。
それだけではない。人を想い涙を流せる人にもなった。
けれどやはり、彼女は骨の髄まで円成寺の女なのだ。
「そういうわけで、お兄様――」
初めて兄と呼んだ琴子の表情を、壮士はその生涯を終えるまで鮮烈に記憶することになる。
桐山壮士はこのとき初めて円成寺琴子の本質に触れたのだ。
「わたくしと一緒に“人を殺す練習”をしましょう」
ぞくぞくと怖気が走り、肌が泡立つ。
どうして彼女はこんな言葉を、こんなにも愛らしい顔で告げられるのか。
もはや倫理道徳という概念そのものが欠落してしまっているように思う。
琴子の想いはどこまでも白く純粋で、なのに彼女の人間性は黒くて悪辣《あくらつ》だ。
白と黒。相反する二つの色。
それらが混じり合って灰色になることはなく、厳然と色合いを保ちながら彼女の内側で共存してしまっている。
壮士は思う。
――ああ、兄貴はこんな気持ちになったのか。
――きっとこの子は兄貴と心の為ならなんだってやるんだろう。
認めるしかない。兄同様、壮士はこの少女の本質に恐怖したのだ。
琴子の持つ黒さは抜き身の刃のように危うく、そしてその危うさは、白き想いの強さに比例して他人を無慈悲に蹂躙してしまうだろう。
選別の基準は明白だ。“大切な人”と“それ以外のすべて”だ。
不憫に思う。琴子の愛情は正当ではあるけれど正道ではない。
「人殺しの練習なあ……」
そう呟きながら壮士はふと気づいた。思えば彼女にプラスの感情を覚えたのはこれが初めてかもしれない。たとえそれが同情心だとしてもだ。
ずっと琴子に複雑な感情を抱いていた。
あんな無体なゲームを強いられ、それでも彼女は精一杯生きた。時々において選択し、あるいは諦め、そして大切に思う人を救おうと懸命だった。
判っている。琴子は何も悪くない。悪いどころか彼女は一馬と心の命を救ってくれた恩人だ。そう頭で理解していて尚『この子さえ居なければ』という想いが拭えないでいた。
改めて琴子を見る。
変わらず彼女は微笑を浮かべていて、肉親を見るような柔らかな眼差しをこちらに向けていた。
ジッと見つめている内に気づきが降って湧いた。
彼女に対して自分がどうあるべきか、壮士はその答えを見つけられた気がして――。
「琴子ちゃん」
「はい、お兄様」
琴子の愛情は歪で邪道だ。
けれど、それでいい。それがいいだろう。
だって壮士と琴子は悪魔の手先に成り下がった。邪道こそ相応しいというものだ。
この子の歪んだ愛情は、いつかきっと兄や心があるべき姿へと導いてくれる。だから彼らを取り戻すまでの間、二人に代わって自分がこの子を愛してあげよう。そして彼女が正しく人を愛せるその時まで、決して死なせはしない。
それが壮士の役割だ。あるべき姿だ。一馬ならきっとそう考える。
壮士は『ったく、めんどくせえな』と口のなかでだけ呟くと、苦笑いして琴子にこう告げた。
「人殺しの練習もいいけどさ。まずは俺と一緒に飯でも食いに行かないか」と。