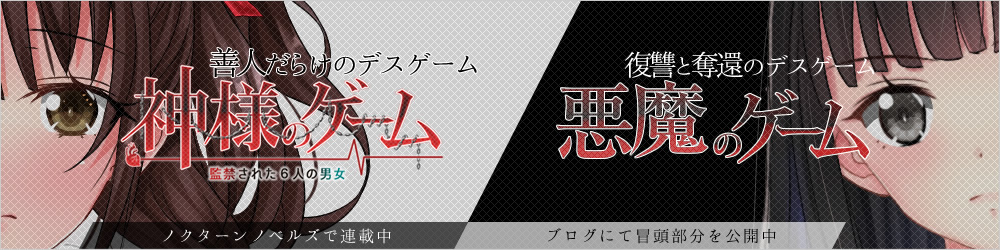「だから神と答えろと忠告してくださったのですね……」
澄と北岡の双方が、敵陣営を内部から侵すべく送り込まれたスパイ。
しかもそれは陣営の主《あるじ》――神と悪魔それぞれが、みずから主導した戦術だとするなら、これまで琴子が覚えた不可解なことの数々に説明がついてしまう。
・北岡が澄に引き合わせる前に琴子の所属を知ろうとしたこと。
・壮士の回答を事前に把握しようとしたこと。
・神と答えるよう忠告してきたこと。
・琴子が悪魔と答えようとした際に制止してきたこと。
・繰り返し琴子の所属を確認してきたこと。
これらのことすべてに、北岡の真なる所属が悪魔であるという前提を敷くなら得心がいく。
それだけじゃない。北岡の告白は道義的な面でも信じるに値する。
「食べ物や薬のアレルギーはありませんか?」
「? いや、ないけど……」
「ではこちらを。抗生物質です。敗血症を防いでくれます」
琴子は錠剤と小さなペットボトルを手渡し、止血剤を用意。
その傍らで思考を続けていく。
(北岡様が方針を変えたのは一馬様たちのことを話したあとだった)
それもまた、北岡の本当の所属が悪魔であることの傍証だと思えた。
あの話をするまでの北岡は、明らかに澄を優先するスタンスを取っていた。
琴子を殺すことに消極的だった一方、積極的に生かそうとはせず、まして壮士の生き死になんて気に掛けていたのかすら疑わしい雰囲気だった。
そんな北岡がしたことは、琴子が生かされる可能性が上がる――かもしれない、という程度の些細なヒントを与えたくらいが精々。有り体に言えば「まあ、運良く生き残れたら」くらいの温度感でしかなかったんだと思う。しかも、そのなけなしのモチベーションでさえ「まだ子供だから」みたいな、安い偽善のたぐいでしかなかったはずだ。
実際これは出会った当初に北岡本人が口にしたことだ。
(だけど、この人は)
北岡はちゃんと琴子を見てくれた。怒り、渇望し、地べたに這いずって怨嗟を吐く琴子に「すまなかった」と謝ってくれた。「嫉妬したんだ」とも言っていた。
あの瞬間に、彼は内にある優先順位を変えてくれたんだと思う。
変えてくれたから、北岡は自分が撃たれて尚、琴子のことを身を挺して庇ってくれたのだ。
他にもある。
北岡の告白を以って琴子がもっとも腹に落ちたことは、
(佐橋さんは多大なリスクを被ってまでわたくしを生かしたこと)
これはどうだろうと、琴子は今一度考えてみた。
あのときは『澄の善良さ』と評価したものの、彼女が神の手先であるなら、あのお人好しな判断にも別の解釈が生じることになる。澄の立場が裏返る以上、彼女がいま被ろうとしている不利益も一緒に裏返るのは必然だ。
北岡の味方を増やすこと、琴子の味方を増やすことは自陣、即ち神側の勝利に資することだ。
もちろん澄は真実悪魔の所属なのだから、以降、北岡たちと行動をともにすることはできなくなるが、スパイの仕事としては良い働きだと評価していいだろう。
「それにしても驚かされました。佐橋さんのみならず、北岡様までもが……」
そう口にするまでに費やした時間はほんの数秒ほど。
しかしそんな色々を目まぐるしく思考している琴子に、北岡が苦しげに言った。
「本来敵同士の俺たちがっ、なんで手を結んでいると思う……?
お前の読み通り、初戦で俺は佐橋を助けたし、佐橋が俺を助けてくれた場面もあった。協力して勝ち残ったのは事実だ。ぜんぶ成り行きだったけどな……」
「しかしだからといって」
琴子は少しでも北岡の負担を和らげるべく、彼の言わんとすることを引き継ぐ。
「そう簡単に敵と手を組めるわけがありません。
ひとつ間違えば本当に殺されてしまいますからね」
琴子の気遣いを察してか、北岡が「そういうことだ」と苦笑を浮かせた。
「本当のところ、佐橋が腹のなかで何をどう考えているのかはしらん。しらんが、少なくても俺のほうは完全に打算ありきの関係だ……」
北岡が澄と手を結んだ本当の目的。
それは澄が悪魔所属のプレイヤーを殺害することを阻止、あるいはコントロールすることを目的にしていたのだと、北岡は言う。
「理解できます」
前者は当然だ。いざ悪魔側のプレイヤーを殺すとなったら、同陣営である澄も相応の理屈を付けると思うが、とにかくこちらとしては味方を狩られては困る。
後者についても共感できる。澄の殺しのすべてを阻止することは現実的に不可能だ。
二人が一緒に参加できないゲームは勿論のこと、ルール上阻止できないケースだってあるだろう。もっと言えば北岡自身、澄が殺害しようとする者が本当に悪魔の所属なのか知るすべがない。
なのですべては止められない。が、すべてを止める必要だってないのだ。
敵方の殺しに介入できる立ち位置を確保しているだけで意味がある。
琴子は内心「我ながら意地が悪い」と自覚しつつ敢えて尋ねてみた。
「しかしそれなら佐橋さんを殺してしまうほうが手っ取り早くないですか?」
北岡は苦々しい顔で答えた。
「いい子なんだよ……。恩もっ、借りもある……」
「ですか」
まあ、そうなのだろう。
北岡は打算ありきだと言うけれど、しかし打算だけは敵に命を預けて戦えはしない。
北岡が口にしたように、澄に対して恩や借りを覚えているから、彼は撃ち殺されるリスクを負ってまで澄に配慮した。いいや、できたのだ。
そのくらい北岡は澄の人柄に信頼を寄せている。互いの立場はそれとしてだ。
琴子は傷の具合を確認しながら言う。
「出血がやや収まってきたようです」
「それは良かった……にしてもッ……、いってぇなっ……、どこのどいつだ、撃ってきたクソ野郎はっ。あとでぜったい見つけ出して殺してやる……」
琴子に言わせれば、澄の仕業というセンがまだぜんぜん生きている状況なのだが。もしそうなら北岡は澄を殺すのだろうか。それともエッチなお仕置きくらいで許してあげるのだろうか。
そんな益体もない感慨を覚えつつ、かなりつらそうな北岡の様子を受け、琴子が腕組みして考え込んでいると、
「とにかくだ。要点は伝えた。ダラダラしゃべってないで早く逃げろ……」
「まだ北岡様が撃たれてから、カップ麺ができるほどしか経っていないと思いますけれど」
そう言う琴子はカップ麺を食べたことがない。
ハンバーガーはお兄様に食べさせてもらったことがある。あんまりおいしくなかった。
「3分も経ったってことだろ……」
「見捨てないと言ったはずです。傷の処置もまだ終わっていません」
「頑固なやつだな……」
相変わらず廊下を警戒しながら呆れる北岡。
琴子もひょっこり廊下を覗き込んで、右へ左へと首を振ってみたが、
「静かなものです。このぶんなら追撃はないかもしれませんよ?」
「……お前はなんというか、少しくらい動揺したらどうなんだ?」
「その目は節穴なのですか? 今しがた狙撃を受けて、目の前には血まみれの男性ですよ。動揺しているに決まっているではないですか」
「可愛げがないガキだな……」
「結構ですっ。貴方に可愛く思われなくたって痛くも痒くもありませんからっ。一馬様とお兄様がわたくしを可愛いと褒めてくださいます」
「お前はあれだ、突き抜けた楽天家か、底なしの馬鹿のどっちかだな……」
琴子は不快げに顔をしかめて、傷を押さえる手に力を込めた。
「ぐっ、ぅ……」
「やはり鎮痛剤を打ちましょう」
「そんな物まで持っているのか……」
「ええ。医療用に調整された物とはいえ、それでも麻薬であることには違いありませんから。副作用の兼ね合いから様子を見ていましたけれど、とてもお辛そうですし。弱めの薬なら軽微なもので収まると思います」
それにもし、ここから交戦とするとなったとき、軽微な副作用で被るデメリットよりも、北岡の痛みを和らげることで得られるメリットのほうが上回るという判断だ。
痛みで北岡の動きが阻害され、それで琴子が殺されては目も当てられない。自分で言うのは悲しいけれど、琴子の戦闘力は凡以下。骨の髄まで北岡を頼らせていただく所存である。
加えて言えば、
「手当をしているあいだに話を続けましょう。まだまだお聞きしたいことがあります」
そうさらりと口にしながら琴子はその実、壮士のことが気掛かりでならなかった。
北岡の告白を受け、状況がより複雑になってきている。澄の腹の内、澄が壮士に取るアプローチがまるで読めなくなってしまった。
依然として情報が不足している。今のままでは算段の立てようがない。
「なにが聞きたい……」
あれ以降、澄から連絡が入っていないのも気掛かりだ。
曲がり間違って狙撃手が澄であったなら、決して良くはないが最悪ではない。それなら彼女は壮士と接触していないということになる。
このケースなら、澄がインカムを持っている兼ね合いから壮士と合流できる目が遠のくものの、兄の身の安全という面では安心材料となる。
最悪なのは今回の狙撃が、澄が手引きした第三者の手によるもの、かつ澄自身は変わらず壮士と接触するつもりだというセンだ。
もしそうなら壮士の身が本当に危うい。だからこそ、
「佐橋さんが神のスパイだと考えた、その根拠を聞かせてください」
「ああ、その話をしていなかったな……」
北岡が挙げた根拠は二つ。
「一つは初戦だ。ゲームの内容は省いて要点だけ話す……」
北岡と澄が挑んだ初戦。それは神と悪魔それぞれの陣営から三名が参加する、合計六名で争うというものだったという。
初戦における紆余曲折は省略するとして、最終的に三人が勝ち残った。
三人の内の二人は無論、北岡と澄であり、
「最後のひとりは女、歳は佐橋とそう変わらないように見えた。名前は……立花だったかな」
その立花なる女が北岡に気づきをもたらした。
「確信がある。二人とも上手くごまかしていたけど、佐橋と立花は面識がある……」
「その立花という人は――」
「神だ」
「……なるほど」
「これはそこまで自信を持っているわけじゃないが、二人の関係は知り合いってレベルの浅い間柄じゃないかもしれない」
事実、二人は互いの存在を認識して以降、それとなく協調するような立ち回りをするようになった。
「最初に顔合わせしたとき、ほんの短い時間のあいだだけ“立花だけ”が“小さく驚いた”ような顔をしたんだよ……。まずそこに引っ掛かりを覚えた」
「小さい、ですか」
北岡が言うには少し目を見開いた程度だったという。
とはいえ驚いてはいるのだから、少なくとも立花にとって、初戦における澄との邂逅は完全な想定外、もしくはそもそも予想してなかったのは間違いない。
だが澄は驚いていなかった。しかしそれでも阿吽の呼吸で立花と協調してみせた。
「佐橋は知っていたんだと思う。立花がこのゲームに参加していることを。下手すると、立花が神側であることまで事前に把握していた可能性まである。
逆に立花は佐橋のことを知らなかった感じだった」
もちろん立花のそれが『なんでお前がこのゲームに?』といった、純粋な驚きだった可能性はある。
「だけど、そんな可能性はゼロだ……」
澄は悪魔。立花は神。たまたま知り合いだった二人がデスゲームの初戦で邂逅し、阿吽の呼吸で協調体制を取れる確率。
あり得ない。その確率は完膚なきまでにゼロだ。
「知り合いならどうしてもっとあからさまにしない? 目で会話したり、サインっぽいのを送り合う? そんなことをする理由は、俺や他のプレイヤーに関係性を気づかせたくなかったからだ。そうとしか思えない……」
琴子は敢えて異論を唱えてみる。
「二人が敵対陣営に所属していたからではないでしょうか。敵同士の二人があからさまに協調すれば、同陣営の残る二人の心証を損ねてしまいますよね?」
言いながら琴子はアンプルから小型の注射器に薬液を抽出。
目で打つぞと問いかけると、北岡は大いに顔をしかめた。
「それほんとに大丈夫なのか? 素人が注射って危なくないか?」
「…………」
琴子は無視して打った。
「痛みを和らげる程度ですが、直ぐに効いてくると思います。それで、佐橋さんと立花さんは同陣営の方たちの心証を気にしていたのでは、という話ですけれど」
「そんなもの気にする必要がない。所属を明かしはしたが、初戦は陣営間で争う内容じゃなかった。個人が勝ち残るゲームだったんだよ……」
その証拠に北岡が挑んだ初戦の勝者は、神の所属が二名、悪魔の所属が一名、という内訳で決着している。
「だいたい同じ陣営たって、顔も見たこともなければ話したこともない奴らだぞ? 手を組むならどう考えたって知り合いが優先だろ。命が懸かっているんだから……」
それでも二人は関係を隠そうとした。
「もうじゅうぶんだろ……」
「お考えは理解しました」
つまるところ北岡は、澄と立花は共通する何かしらの『背景』を持っていると推察したのだろう。
背景とは経験かもしれない。事情かもしれない。
そこは分からない。
澄は、立花がこのゲームに参加していることを事前に把握していたと考えられる。だって澄は立花との邂逅に驚かなかったのだから。
そして驚いた立花もまた、澄のなにかしらを知っていると推察される。
ただの知り合いであるはずがない。顔見知り程度の浅い関係ならば、周囲に悟られないよう澄と協調して事に当たると思えない。
立花が驚いた理由は概ね三つに絞れると、琴子は考える。
(佐橋さんが悪魔のゲームに参加していたことそのもの。佐橋さんが悪魔の所属であること。あるいはその両方に驚いたか。どれかでしょうね)
これは単なる直感に過ぎないが、琴子の感性は「両方じゃないか」と告げていた。
北岡が続ける。
「もう一つの根拠は俺自身だ……」
北岡は自身が敵陣に送り込まれたスパイであるが故に、その存在をゲームが始まる前から認知していた。自身がスパイが存在する証拠でもある。
とどのつまり、なにが言いたいかというと、
「俺の同類が神の側にもいるはずだ」
「……ちょっと待ってください」
琴子はほとんど脊髄反射的に手を持ち上げた。
ちょっとしたニュアンスの違いだと思うが、今の発言は聞き捨てならない。
「いる“はず”ではなく“確実に”いますよね?」
何故なら陣営間の公平性は保たれる。北岡が味方のフリをして神の手先を狩るというなら、神の側にも同じ役目を負う者が存在しなければならない。
でなければ嘘になる。少なくとも神は決して嘘をつかない。
故に居る。琴子や壮士の寝首を掻こうとする者が。必ず。
だが、北岡は首を振った。
「いいや、十中八九いるだろうけど確実とまでは言い切れない。これは同じツッコミを入れた俺に、悪魔が言ったそのままのセリフだ」
「……どういうことですか? 陣営間の公平性は保証されるはずですよね?」
北岡が悪魔の言い分を教えてくれた。
『貴殿は神側のイチプレイヤーに過ぎません。
なにを以って公平性を毀損する存在だと言うのですか?』
琴子は言わずにいられない。
「それは屁理屈というものでしょう?」
「そうか? 俺は言われてみれば確かにって納得したけどな」
琴子は改めて考えてみる。
北岡は公平性を毀損する存在か否か。
するんじゃないか。
だって北岡は悪魔から特定の役割を任されて敵陣に送り込まれている。北岡は神側に所属していていても、実際は悪魔側のプレイヤーとカウントされるべき人だ。
しかし神側にはそのような存在が必ずしも用意されているわけではない。だったら、
「プレイヤーの人数という側面だけ見ても不公平だと思いますけど?」
北岡は直ぐに切り替えしてきた。
「思想信条が別であっても俺は真実神側のプレイヤーだ。神と悪魔で駒の数が同じなら公平だろ」
「…………」
それは詭弁じゃないか? と言いたくなるも、琴子は結局ぐうの音も出せなかった。
確かに北岡は、神が自陣のプレイヤーに求める、あるいは神側のプレイヤーが取るであろう行動理念に沿って動かないだけで、神側のプレイヤーであることは揺るぎない事実だ。
琴子はそれを屁理屈だと言っているわけだが、屁であっても理屈は通ってしまっている。
「なんだか釈然としませんけれど、ではそれはいいとしましょう。しかし現実問題として、スパイを送り込むなんて実現できるとは思えません」
「そんなこと言ったって、現に実現している俺がいるじゃないか」
「どのような手段を用いて神の陣営に?」
神に露見しないまま潜り込めるとは到底思えない。
幼女のような言葉遣いな神はしかし、決して馬鹿ではない。その下衆な性格はさておくとしても知性は非常に高く、知恵も回る。抜け目もない。なにせ神様のゲームの考案者だ。
「カムイに口を利いてもらった」
「……なんですって?」
またもや耳を疑う発言が飛び出してきた。
「カムイさんが神を裏切ったということですよね? 信じれません……」
「いや、その辺りの細かい事情は俺にもわからない。スパイの件は悪魔が俺に依頼して、悪魔からカムイ、カムイから神、神から俺って流れでまとまった話なんだよ」
「ああ……」
そういうことかと琴子は納得した。
神は当たり前に北岡の正体に気づいている。そして悪魔は、たとえ神に気づかれたところで、神は嬉々として北岡を受け入れるに違いないと、そういう目算があって神威に話を持ち掛けたのだろう。
琴子ですらそんな予想がついてしまうのだから、神の性格をより熟知しているであろう悪魔は言わずもがなだ。
「バレていますよ」
「バレたところで神は何もしてこないし、絶対に口外もしないだろうって悪魔は言ってたな」
さもありなん。
スパイなんてゲームをより楽しくさせるスパイス要素を、あの邪神がみずから排除するはずがない。
悪魔もそうだ。北岡に準ずる神側の存在を、高い確度で受け入れていると推察する。
さらに言えば、ゲーム開始当初、悪魔は「神殺しを成すその時まで会う機会はない」と口にしていた。即ちゲームが始まってしまっている今、もはや神と悪魔の直接介入はないと言っていい。
現時点でゲームマスターからプレイヤーにスパイの存在が明かされる機会は失している。
「マアさんとカムイさんはスパイの存在を把握していると思いますか?」
「わからん。マアは顔合わせした程度だし、見当もつかない。ただカムイに限って言えば、俺の正体に気づいた様子はないな。たぶん相当な馬鹿なんだよアイツ」
「そうですか……」
そこそこ辛辣な言葉だが、そう感じている琴子にしたって、神威のことを「頭が弱そうな子」と評価しているわけで、なんとも言いづらい。
一応琴子としては、以前に神威を騙し討ちまがいに殺しちゃった負い目もあって、個人的には仲良くしたいと思っている次第である。
けれど残念なことに、今回は神威の名誉を回復してやれそうになかった。
ともあれ、
「スパイ自身に何かしらの制約、逆に特典のようなものはあったりしますか?」
「一切ない。誰に話すも明かすも自由だし、お得なことも何もない。所属が裏返っていること以外は単なるイチプレイヤーだ」
これについては予想通りだ。
神と悪魔にとってスパイは言わば公然の秘密のようなものだが、それでも秘密は秘密だ。
スパイは公平性を毀損しないとする以上、神と悪魔はスパイに対し、他のプレイヤーに無い特別な力や優位性を与えてはならない。
それは禁忌だ。目に見える形で公平性に齟齬が生じてしまう。
そこで北岡が今一度、澄を神の手先だとする根拠をまとめるように言った。
・神の手先が悪魔側に潜り込んでいることはほぼ確実。
・悪魔の所属である澄は、神の所属である立花と浅からぬ関係にある。
・立花と出会ったところで大して驚きはしなかった。
・立花と協力しながら、しかし関係は伏せようとした。
・北岡と琴子を簡単に殺せる状況だったのに殺さなかった。
・むしろ自分が不利益を被ってまで、北岡と琴子が手を組めるようお膳立てしてくれている。
琴子は顔を渋くさせながら問う。
「ちなみに北岡様と佐橋さん、手を組もうと声を掛けたのはどちらですか?」
「佐橋だ」
つまり澄は、自身と面識があり、協調した立花を選ばず北岡を選択した。
立花も北岡も同じ神の所属であるにも関わらずだ。
(これはどうでしょう……)
澄が自身の身の安全“だけ”に重きを置くなら、たったいま出会ったばかりの北岡よりも、知己がある立花に誘いを掛けて然るべきじゃないか。
手を結んだ効果のほどは、澄と立花が初戦を通じて証明している。
「うん……、その件は根拠になりませんね」
澄は真実悪魔の側に属している。このゲームが陣営の勝利を目指すという性質上、北岡であろうと立花であろうと、いつか衝突するのは避けられない。
だったら身の安全もなにもあったものじゃない。
北岡と立花にとって、澄は敵性存在でしかないのだから。
スパイの仕事をする面でも両者に大きな違いはないと思う。
彼・彼女は神の手先。北岡も立花も殺害対象は悪魔側だ。仕事のやり易さの面で違いはあるかもしれないが、その点を澄がスパイである根拠とするのはさすがに無理筋だろう。
ゆいいつ立花と与するほうが優れている点があるとするなら、それは澄と立花の関係性に依るところが大きい。たとえば衝突が不可避となった場面において、立花であれば手心を加えてくれる余地がある。
しかしそれだって、もし二人の関係性が良好でないなら、北岡と組んだほうが良いという話になってしまう。
いま琴子が持っている情報だけではエビデンスに数えられない。
「もう一つだけ聞かせてください。
北岡様の正体を、佐橋さんに気取られていない確信はお持ちですか?」
北岡はわかりやすく顔をしかめた。
「ついさっきまで確信があった――としか、今はもう言えないかな……」
「そうですか」
澄にバレていないと確信していた北岡は、今現在襲撃を受けている最中だ。
こちらを殺す動機を持たない澄はしかし、もし北岡の正体を察知していたなら、一気に下手人の最有力候補に躍り出てしまう。
まして澄には襲撃を図るに適した環境的事由が揃いに揃っているのだ。
なんなら澄が北岡の正体に気づいているというセンが、もっとも現状に即していると言っていいくらいだ。
「どう思う?」
その北岡の問いは、澄が神の手先か否かというものであり、
「嫌疑を掛けるには十分な材料が揃っていると考えます。けれど北岡様と同じ温度感で断じられるかというと、少なくない躊躇いを覚えますね」
北岡の反応はあっさりしたものだった。
「まあ、それは仕方ないんじゃないか……」
「と、思います。わたくしはこの目で佐橋さんと立花さんの様子を見ていませんから。
それにこの襲撃についても、北岡様とわたくしが移動しているあいだに、他のプレイヤーに見られていた可能性を否定できません。
もしそうなら、わたくしたちの落ち度です。冤罪になってしまいますね」
「確かにな。だったらこれはどうだ。今からでも佐橋に救援を頼むって俺が言い出したら、お前はどうする?」
そこで琴子はふと気づいた。
「口の周りが良くなってきた気がします。いくらか痛みが和らぎましたか?」
「ん? ああ、言われてみれば……。かなりマシになった気がする。助かったよ」
「いいえ、助けていただいたのはこちらです。くれぐれも安静にしてくださいますよう。所詮は薬で脳を騙しているだけで、重傷を負っていることに変わりありませんから」
「了解だ」
苦々しい顔をして言う北岡は、さながら医者に叱られる患者のようで。
琴子は自然と頬を緩ませつつ、話を本線に戻す。
「それで、佐橋さんへ救援を依頼するかどうかですが……」
琴子は迷い、言い淀んだ。
北岡から話を聞けたことで、いま得られる判断材料は出尽くしている。しかし判断するにあたりもっとも重視すべき澄について断定できることがほとんど無かった。
だったらどうすべきか。
そんなものは最初から決まっている。
(お兄様とわたくし以外のすべてを切って捨てるまで)
琴子個人の利益を最大化させること。それ以外の判断基準などありはしない。
北岡には恩義がある。
縁もゆかりもない琴子を身を挺して庇ってくれた。自分は血まみれになっていながら琴子に逃げろと言ってくれた。もはや彼は疑いを挟む余地のない味方だ。しかしそれでも北岡は琴子の一番ではない。
澄もそうだ。
琴子の見解では、彼女への疑いは未だ嫌疑の域を出ないものだ。澄が神の手先なら当然殺すべき人だが、そうでないなら協力者として魅力的な人物でもある。
しかしながら澄もまた、壮士や自分を脇においてまで慮《おもんばか》る対象ではない。
であるなら、おのずと結論できる。
「佐橋さんに救援を要請しましょう」
そうするだけで壮士の身の安全が叶うのだから。
澄を呼び戻すことで生じるリスクはすべて負う。
たとえ澄が神の手先であっても、襲撃に関与していても、主犯であろうと追撃を助長しようと、澄が傷を負った北岡を見て変心したとしても、結果恩人である北岡や自身の命が危険に晒されようとも関係ない。
そんなものは琴子が対処すればいいのだ。
壮士のほうがずっと大切だ。
そんなこちらの思いを、北岡は察していたのかもしれない。
「そんなことならサッサと逃げときゃいいのに。俺に構うから」
北岡は意地悪っぽく笑って、腰から無線機を引き抜いた。
「いいぞ、それで。まずは桐山の安全を確保しようじゃないか」
「ありがとうございます。呼び戻すとして、佐橋さんをどうしますか?」
「もちろん捕まえて吐かせる。こうなったらもう佐橋本人に聞くしかないだろ」
「ですが貴方様は相当な深手を負われています。十全な状態であればなんの心配もしませんが、……いけますか?」
「こっちは二人だし、不意打ちもできるんだ。佐橋が襲撃に関わっていなけりゃ問題ないだろ」
「もし関わっていて仲間を引き連れてきたら?」
「そのときは俺を担いで逃げてくれ」
「無茶いわないでください……」
「ま、その辺りのことは、あいつが戻ってくるまでのあいだに練ればいいさ」
悪い顔色ながら軽い調子で言って、北岡は無線機のボタンを押し込んだ。
「佐橋。いま話せるか?」
ブツリという音が鳴り、しかし無線機からはなんの音も返って来ない。
「佐橋。聞こえるか?」
やはり返事はない。
北岡の顔つきが険しいものに変わっていく。
「なにかあったか? 一言だけでもいい。応答しろ」
北岡がなんど呼びかけようと短いノイズ音が聞こえるだけで、澄の声は届いてこない。
「……どうなってる?」
北岡が怪訝に呟いた刹那、琴子の背筋にぞわりと冷たいものが走った。
「ジャミングされているかも……」
ぼんやりと口にした琴子に、北岡が大きく目を見張った。
「無線が妨害されているって? いや、いくらなんでもそれは考えすぎだろ……?」
「50メートルです」
琴子は頬を引きつらせ、弾かれるような勢いで廊下を覗き見た。
釣られて北岡も廊下の様子を伺いながら、
「なんの数字だ」
「民間で手に入る通信抑止機器の妨害範囲です」
「そんな馬鹿――」
北岡がその可能性を否定しようとした瞬間――。
「ぉ―――」
「ッ……!」
突如として階下から炸裂音がとどろき、建物そのものがかすかに揺れた。
北岡が戦慄を顔に刻んで呟く。
「おいおい、冗談だろう……?」
琴子もまた唖然とした顔を浮かせて北岡に問う。
「今のはトラップが作動した音……ではないですよね?」
「そんなわけないだろ……。トラップごと爆破したのか……?」
言っているあいだに、もう一度爆音が轟いた。
「滅茶苦茶です……。こんな派手な音を響かせて鬼に聞かれでもしたら……」
「通信妨害までして爆破って、どんだけ殺意高いんだよ……」
二人がとぼけていられたのはそこまでだった。
直ぐに二人は我に返って互いを見合った。
琴子は慌てて銃を引き抜き、シリンダーを開けて、弾数を確かめながら大喝する。
「高い確度で相手は最大三名と予想します! 迎え撃ちますか!?」
「なんでそんなことがわかる!?」
北岡もまた怒鳴り返しながら、持ち弾を確かめていく。
「悪魔から言質を取っていますッ!」
「相手が同数だったとしても迎え撃つのは無理だ! 爆弾持ちだぞ!? 手榴弾の一つでも放り込まれたらそれで――ぐッ、ぅぅ……」
腹を押さえて苦鳴を上げる北岡。
もはや選択の余地など、どこにもありはしなかった。
「逃げましょう!」
決断して、琴子が北岡に肩を貸そうとした時には既に手遅れだった。
コツっと音を鳴らせて、廊下に拳大の円柱が投げ込まれた。
「――――」
「――――」
すわ手榴弾かと思われたそれは、猛烈な勢いで白煙を撒き散らし始めた。
同階まで踏み込まれたことを悟り、北岡は即断した。
「俺が足止めするッ! お前はお兄様を助けに行けッッ!」
「ですがっ……!」
「歩くのも苦労する俺を連れて逃げ切れると思うか!? 二人とも殺されるのがオチだッ!」
怒号して、北岡は煙の向こうに銃弾を放つ――と、即座に廊下の奥から応射があった。
放たれる銃声の数を耳にして、北岡はギリッと歯を軋らせた。
「相手はたぶん二人だッ! めくらでいいから撃ちまくれッ!」
「はい!」
言われるがまま、琴子はありったけの弾を放っていく。
その間に新たなマガジンに交換した北岡は、牽制を目的にトリガーを引きつつ、
「今の内にリロードしろ! 俺があと7発撃ったら次はお前が撃て! その次に俺が撃っているあいだに防火扉に向かって走るんだ。いいな!?」
「~~~~ッ、わかりましたッ!」
琴子は歯噛みしながら新たな弾をシリンダーに込めていく。
その間も相手側の銃弾が風を唸らせて過ぎ去り、北岡は適時応射しながら意図的に声をひそめ、けれどまくし立てるような勢いで琴子に告げた。
「防火扉の先に貨物用のエレベーターがある。それで一気に1階まで降りろ。ここから下の階のボタンは壊してあるから、そこから敵が上がってくることはないはずだ。この経路なら相手に挟撃要員がいたとしても鉢合わせする可能性は低い。もし出くわしたら自分でなんとかしろ。
ビルの正面から右手、50メートルくらい先に地下鉄への降り口がある。佐橋が嘘をついていないなら待ち合わせ場所はB11番出口近くだ。覚えたか?」
「覚えました! 準備できています!」
「持っていけ」
北岡が琴子の胸に無線機を押し付ける。
琴子が黙して頷き、無線機を尻ポケットにねじ込んだのを見取って北岡は叫んだ。
「撃て!」
「はい!」
そうして映画さながら銃撃戦を繰り広げているあいだにも白煙が空間を侵食するように充満し、フロアのなかまでその侵食範囲を広けていく。
互いの顔さえ判然としなくなっていくなか、北岡の落ち着いた声が届いた。
「円成寺」
「なんですか!?」
「さっき話した佐橋の件はぜんぶナシだ。お前が思うようにすればいい」
北岡の声があんまりにも平坦で。自然、琴子の内に灯っていた昂りが急激に冷めていく。
琴子は絞り出すように答えた。
「承知、しましたっ……」
「頼みがある」
「なんなりと」
「もし佐橋の正体が神の手先だったとしても、できることならあいつの命は取らないでやってほしいんだ。憎いだろうが見逃してやってくれ」
「お約束します。一馬様に誓って」
「ありがとう。それなら安心だな」
「最低でもお兄様を連れて戻ります。それまでどうかご無事で」
頑張ってみるよ、と白色が満たす世界の向こうで北岡が苦笑いしていた。
「最後にもう一つだけ伝えておく」
「縁起でもないことを言わないでください」
「悪魔が言っていた。『悪魔のスパイは二人いる』って。俺と同じ役目を負っている奴を、別ラインでもう一人送り込んでいるんだそうだ」
「北岡様と同じ立場の方がもうひとり……?」
「そいつを探せ。名前も性別もわからんが、どうにか見つけ出して仲間にしろ。信用できる。もう死んでいたらしらん」
「かしこまりました。ご助言感謝します」
北岡が血で汚れた手でそっと琴子の頭に触れた。
「大切な人たちを取り戻せるといいな。今度はちゃんと告白して、受け入れてもらって、それから結婚したいってお願いするんだぞ?」
「ふふ、確定している未来だと申しましたのに」
「一方的なのは駄目だ」
「ですね」
柔らかに微笑みあったことを、琴子は強く記憶に刻む。
だけど、あともうひとつだけ。
「お名前を」
刹那の空白を挟み、可笑しそうに喉を鳴らす音が聞こえた。
「克己《かつき》だ」
「北岡克己様。覚えました」
きっと忘れまい。きっともう会えないだろうから。
でも。でももしまた克己と会えたなら。今度は名前で呼び合うような関係になりたいと思う。
「行けッッ!」
「ッ―――!」
克己が放つ銃声を背に受けながら、琴子は廊下をひた走った。