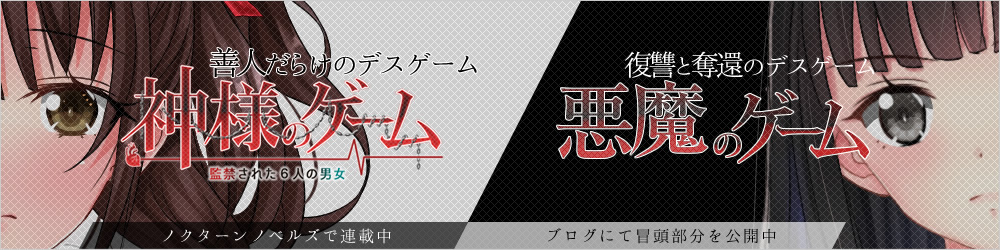「う~ん。これはむずかしいぞ……」
難しい顔で唸って、首をひねる神威。
眉をハの字に曲げたその顔は真剣そのもの。しかし一歩下がって全身を視界に収めれば、いかに彼女が適当に悩んでいるのかわかる。
神威の手元では、どこの大道芸人かと見紛うばかりにリボルバーがクルクルと回されていた。
「どっちの脳みそがぶちまけられるんだろうなあ……。円成寺だったらいいなあ……」
じっさい物騒な呟きを漏らす神威の声音は実に愉しげだ。
彼女の持つ銃には既に6発の弾丸が込められてある。
装填作業は神威が務めた。
これは手札を明かした後、必ずどちらかが死ぬが故の措置だ。双方が賭けた弾からそれぞれ3発ずつ、二人の目の前で装填された。
「むむっ」
と、不意に神威の尖った耳がピクリと動いた。
暫くの間、彼女は瞑目しながら「ふむふむ」と唸って、
「ママとじーちゃの予想は同じみたいだね」
「予想? 神様たちはもう結果がわかってるんじゃないの?」
まるで日常会話のような温度感で花子が問いかける。
その軽快な話しぶりから、彼女がこの一戦に絶対の自信を持っていることが伺えた。
「ううん。それだとつまんないでしょ? だからママたちは手札みないようにしてる」
神威のあんまりな言い草に、琴子は呆れの吐息を漏らさずにいられない。
「まさに見世物ですね」
「そだよ? わかってたことじゃん。バカなの?」
はいはい馬鹿ですね、と琴子は苦笑い。
いまさら腹は立たないし、なんならいっそ清々しさすら覚えるくらいなのだが、いい加減にかの件を許していただきたいものだ。琴子は悪意を持って神威を殺したわけではないのだから。
「それで、あの者共はどちらの勝ちと予想しているのですか?」
「それをいっちゃー面白くないだろ。カムは花子に賭けるぞ!」
ありがとう、と花子はニコリと微笑んで琴子に向き直る。
「どっちから開ける?」
琴子が肩をすくめて『お先にどうぞ』をジェスチャーすると、花子は自らの手札をパチンと指で弾き、それから二枚のうち一枚だけを抜き取り、
「いいわよ。私が先に開ければドヤ顔しなくて済むものね。だいじょうぶ、恥をかかせるつもりはないわ。円成寺ちゃんに個人的な恨みはないし、一億も貰っているもの」
「ご配慮痛み入ります。もっとも、あのお金は返していただきますが」
決着の刻。
「そのすまし顔を崩しちゃ駄目よ……」
花子は溶けた声で囁き、一枚目のカードをテーブルに置いた。
裏向きにしたそれに指を掛け、勿体つけるように緩慢な動作で徐々にカードを表向きにめくっていく。
「……ッ」
「だめ、だめよ……、もう崩れてる」
大きく目を見開いた琴子に、花子は慰めるような優しい声で囁きかける。
「いま言ったばかりじゃない。自分を保って。プライドを護らないと。みっともない死に方したくないでしょう?」
そうして明らかになった一枚目は『ハート8』。
琴子は頬を引きつらせつつ、ぐしゃりと自身の手札を握り潰して叫ぶ。
「ありえません! 0.03%ですよ!?」
「私もそう思う。でも所詮は統計上の数字でしょう? じっさい円成寺ちゃんだってバレッツを引き当てたじゃない。そしてこれがイカサマじゃないってことを、あなたはよく判っている――」
言って、花子はこちらを愛でるような目で見つめ、残る一枚をテーブルに置いた。
「私の方が“天に愛されていた”みたいね」
そんな皮肉と共に明らかにされた『ハート9』。

ハート『8910JQ』のストレートフラッシュが完成していた。
神威は満足気に一つ頷き、それから固っている琴子に目を向けて、
「次はお前の番だ。手札を開けろ」
「ッ……!」
琴子は強く唇を噛み、握り潰した手札を投げ捨てる。
それはもう負けを認めたも同然の行為だ。
しかし、
「チッ」
神威は面倒そうに舌打ちして、捨てられたカードに手を伸ばす――と、
「……認めます」
「あん?」
眉をひそめながら手を止める神威。
一方、花子が勝ち誇った顔で問う。
「なあに? よく聞こえなかった。もっと大きな声で言ってくれないと」
琴子はそんな二人と目を合わせることなく絞り出すように答えた。
「認めます。わたくしの負けです……」
「……認めるんだな?」
そう念を押しする神威に、琴子がかすかに顎を引いた。
それを受け、神威が花子に問うような眼差しを向けると、彼女は小さく首を横に振り、
「勝負はついた」
「……そっか。ならいいよ。二回戦は花子の勝ちだ」
神威の宣言を以って、命懸けのテキサスホールデムは、琴子の敗北という結果で幕を下ろした。
◆◇◆
とある部屋に三人の女が居た。
彼女たちの居る部屋は一面白で埋め尽くされている。ただ、その白色はあまり綺麗ではない。ところどころ塗装が剥げ、錆のようなものも散見される。
そう。彼女たちが居るのは、壮士が戦ったのと同じ造りの部屋。縦に千、横に千、合計で百万を数える部屋群の一室だ。
壮士が居る部屋と唯一異なるのは、部屋の中央に長丸のテーブルが備え付けられていること。
そのテーブルの表面には鮮やかな緑色のフェルトが張られている。テレビや映画などで目にする、いわゆるポーカーテーブルだと思われる。
事実、その使途を裏付けるように、テーブルの上には幾枚ものトランプカードが並べられていた。
そんなテーブルを囲む三人の女。
内二人は殺し合うことを定められ、内一人は殺し合いを捌《さば》く役割を担っていた。
「…………」
殺し合う二人の内の一人――花子は、対面に座る少女を静かに見つめる。
その整った面立ちに緊張や焦燥の色は見られない。むしろ、ゆったりと背もたれに体を預け、口元に微笑を浮かべるその様は、ずいぶんと余裕を感じさせるものだ。
「しょーじき、お前にはガッカリだよ」
花子と少女の中央に立つディーラー、神威がそのルビー色の瞳にありありと失望を映して言う。
「あんだけちょーしこいてたんだし、ソコソコやるんじゃないかって、カム思ってたんだけど。まさか初戦敗退とか! ちょーかっこわるい! お前、期待してくれたじーちゃに謝れよ」
殺された恨みつらみを晴らすように、神威は蔑みを満載に少女を見下す。
そして最後の一人、見下された少女は――。
「こ、こんなものはイカサマです……」
たどたどしく言った琴子の声は震えていて、そしてその青ざめた顔には一欠片の余裕すらなかった。
怯え、色を失う琴子の姿に、神威が喜色の笑みをたたえて言う。
「イカサマねぇ……。約束どーり、カムはちゅーりつにジャッジしてあげたじゃないか。まあ? イカサマだって言い張るなら、どーゆーイカサマしたのか言ってみろよ。お前の言い分が正しかったらゲームをやり直してやるよ」
直後、琴子はどうにか抗弁しようと口を開く。
「ぁ……、ぅ……」
けれど、細い喉が奏でたのは意味をなさない音だけだった。
無理もない。イカサマなど存在しないのだから。
「こんなはずでは……」
琴子は悔しげに唇を噛み、膝の上で拳を握る。
そんな彼女を神威は哀れみの目で見て、テーブルの上に小型のリボルバーを置いた。
「んじゃ、終わりにしようか」
「…………」
神威に促され、琴子は数秒リボルバーを睨めつけると、ぶるぶると震える手を伸ばし、
「あー、ねんのために言っとくけど。自分で死んだほうが楽だよ? もし逃げたら、お前の腕と脚をもいで殺してやるから」
「逃げはしませんッ!」
心外だとばかりに琴子が睨むと、神威は愉しげに「ならいいけど」と嗤い、
「はよ死ね」
琴子は大きく息を吸い、息を吐き、それから冷たい銃口を自らのこめかみに押し当てた。
醜態だけは晒すまい。その一心で瞼を閉じ、引き金に指をかける。
「お兄様……。お許しください」
そんな辞世を呟き、琴子は躊躇うことなく引き金を引いた。
――花子に向けて。
小さく、か細い、声がした。
「は……?」
眼球が飛び出さんばかりに剥き出したその目は、花子の内なる混乱を雄弁に語っている。
一呼吸の間を置かず、真っ赤な染みが穿《うが》たれた右胸を中心に広がっていく。
「ぐっ……ごふッ!」
肺からせり上がってきた血液を吐き出し、花子が椅子から転げ落ちた。
「があああああああ――ッ!!」
肉を切り裂かれ、神経を侵され、発狂しそうな激痛に脳を殴打されて、花子は血反吐を撒き散らしながら転げ回ることしかできない。彼女ができるのは反射的な生体反応それのみだ。転がるごとに新たな血が噴き出し、痛覚が喝采し、花子の脳を激痛の重奏で沸騰させた。
琴子は地べたに這いつくばる花子を無感情に眺めつつ、手慣れた所作でリボルバーをクルリと反転。
「三戦目を」
グリップを差し出す琴子に、神威が唖然とした顔で問う。
「……なにやってくれてんの?」
「? なにか問題が?」
「ロシアンルーレットって言ったじゃん」
そんな質問をされては、遺憾ながら琴子はこう答えるしかない。
「ろしあんるーれっと? なんですそれ? ロシアの郷土料理かなにかですか?」
詭弁以外の何物でもない。無論、そんなことは琴子も判った上で言っている。
だが仕方のないことだ。
先に詭弁を弄したのは神威だ。ならばこちらも詭弁で応えるより他ない。
「……汚え」
「心外です。汚いのはあなたのママでしょう?」
呆れ気味に言った瞬間、神威の全身から殺気が溢れ出した。
瞬きする間もなく、神威の鋭い爪がこちらの瞼に添えられていて、
「もういっぺん言ってみろ……。目ン玉えぐり出すぞ」
「違います! 違います! 神を愚弄したのではありません!」
琴子は慌てて両手を持ち上げての白旗宣言。
一戦目の終わりに「やれるものならやってみろ」と言った時とはわけが違う。
今回の神威は本当にやりかねない。
魔阿と神威はプレイヤーに危害を加えてはならないと命じられている一方、そこに拘束力がないことは既に判っている。
目をえぐられようが殺されようが、ゲームで負けない限り、きっと神か悪魔が生き返らせてくれるだろう。結果、神威が叱られるだけで済むのか、消されるのかは知らないが、琴子としては無駄に痛い思いをしたくないわけで、
「だったらなんだ。ママの悪口は許さないぞ」
「わかっています! 私はただ、このゲームの本質は“神様の御心《みこころ》を正しく理解すること”だと申し上げたかっただけです!」
「アハっ♪」
途端に機嫌を直して、ニパッと笑う神威。
続けて神威は琴子の肩をバッシバッシと叩き、
「なんだよぉ~。それならそうとちゃんと言えよぉ~。殺しちゃうとこだったじゃないか」
「…………」
「どれだけ神のことが好きなんだ」と呆れるのと同時に、「今後はカムイさんの前で神の悪口を口にしないよう、お兄様に釘を刺しておかないと」と心に刻む琴子だった。
一方神威は、胸を撫で下ろすこちらへの関心を失ったのか、軽いステップで花子に歩み寄ると、血まみれの彼女の前でうずくまり、
「おーい、ハナぁ? だいじょーぶかぁ?」
花子はごぼごぼと血泡を吹きながら訴える。
「っ……ごほっ、かむ、ぃ……、なお、して……」
必死に訴える花子の姿は見るも無残と呼ぶ他ない。
鼻と口から体液か涎か鼻水か血なのか胃液なのか、それすら判断できない赤黒い液体を流し続けている。
けれど、そんな彼女の訴えが神威に届くことはない。
「あー、むりむり。カムはママやじーちゃみたいな力つかえないし」
「な、ら……かみさ、たのんで……、ルール……ごふっ、ぃはん……」
「わかったわかった、話はあとで聞いてやるから。ほら立てって。三回戦やるぞ」
事もなげにそう言って、グイグイと花子の腕を引っ張る神威。
琴子は今度こそ深々と呆れの溜息をつくと、神威の隣に並び、
「無茶を言わないでください」
「だって、まだ死んでないし」
「そうですけど……。これ、ホローポイント弾ですよね? 外からは判りづらいですが、花子さんの右肺と血管はズタズタです。とてもポーカーなんてできる状態では……というか、すぐに死にます」
「そうなの? カム肺がどーとか、弾の種類とかしらない。詳しいのな、お前」
「はい、この日に備えて勉強しましたから」
ホローポイント弾とは、弾頭の先端部分がすり鉢状に窪んでいる弾丸を指す。
この弾丸は人体等の水分を多く含む物質に着弾すると、窪みによって貫通力が急減速し、弾頭がキノコ状に急膨張する。
結果、広がった、あるいは分裂した弾頭が内部を巻き込みながら引き裂く、という仕組みだ。
即ち右胸を撃たれた花子の肺は、ただ穴が空いただけでなく、その内部に渡って重篤なダメージを受けている。場合によってはショック死しかねない重傷であり、当然ゲームを続けられる状態にない。
そんな琴子の解説を受け、神威は非難するような眼差しをこちらに向けて、
「だったら頭か心臓撃ち抜いてやれよ。かわいそーにハナ苦しんでるじゃないか」
「そう言われましても、自信がなかったものですから……」
「じしん?」
「わたくし、射撃が下手なのです……」
「いやいやすぐそこだから! 目の前だから!」
「そうですけどっ。ちゃんとした構えも取れないなかで一発しか撃てなかったのですよ? 仕方ないではないですかっ」
血まみれの花子を前に、唇を尖らせて抗弁する琴子。
もしこの場に壮士が居たなら『お前ら状況がわかってるのか』と二人をたしなめただろうが、生憎この場には、少々頭のネジが外れた少女と、人外と、死にかけの女しか居なかった。
「あ~……、まあいいや。ハナもう無理っぽいし、トドメ刺してやれ」
「よろしいので?」
「よろしいもなにも、お前が殺さなきゃだろ。“最終的に相手を殺した方の勝ち”なんだから」
「承知」
サラリと答え、琴子は再度リボルバーを反転。今度は両手でグリップを握り直す。
銃口を向けた先、花子はまだ生きていた。
「――――、…………っ、――――」
が、神威と下らない問答を交わしている間に、彼女は意識を手放してしまったようだ。
琴子はゆっくりと息を吸い、それから丁寧に肺の中を空っぽにする。そうしている間に、短くも濃密な花子との邂逅を思い返してみた。
「ふふ」
自然、口角が吊り上がった。
せっかく花子との思い出を振り返ってみたのに、なにひとつ、まったく、これっぽっちも、特別な感慨を覚えなかった。
予想通りと言えば予想通り。神の手先を殺すことに躊躇いなど覚えようはずがない。
だけど、ほんの少しだけ自分に失望した。
今の琴子を見て一馬はどう思うだろうか、心《こころ》はどう思うだろうか。
そして壮士は、敬愛する兄はどんな顔をするだろうか。
認めてくれると思う。肯定だってしてくれる。琴子の犯す罪を赦してもくれるだろう。
だが、琴子が愛するあの三人は喜んではくれない。
琴子の覚えない痛みを覚え、罪意識を感じ、胸を痛めるに違いない。もちろんそれは花子に対する同情心ではなく、冷酷で冷徹な琴子の在り方を不憫に思ってだ。
ふと、壮士を思った。
兄はとても感情豊かな人だ。
腹が立ったら言わねば損みたいに逐一それを口にするし、可笑しい時は誰はばかることなくゲラゲラと笑う。あんまり機会は多くないけれど、優しくしてくれる時なんかは、彼の柔らかな眼差しに胸がじんわりと温かくなった。
そんな隠し事が上手でない彼が、悲しげに顔を歪ませる瞬間がある。それは決まって琴子がやれ「殺す」だ「復讐」だと冷たい言葉を吐いた時だ。
壮士は一瞬だけ悲しげな顔を作り、しかし必ず琴子に共感してくれる。そうして彼は多くを語らず、優しく琴子の頭を撫でてくれるのだ。
ちゃんと、琴子はちゃんと判っている。
兄は一馬の代わりに、あるいは心《こころ》の代わりに、そしてなにより自分の意思で。
琴子の在り方に胸を痛めているのだ。愛してくれているから。
いつか彼らの望む人になりたい。
いつか彼らが胸を傷めないで済むような人になりたい。
嘘じゃない。彼らの隣に立つに相応しい人になりたいと、ココロの底から願っている。
だから、今は――、
「死ね、神の手先め」
琴子は死に体の花子に向け、残るすべての銃弾を浴びせかけた。
残響が完全に消えた頃、琴子は小さく鼻を鳴らし、物言わぬ躯となった花子の胸元に手を伸ばした。
「これはもう使えませんね……」
血まみれの小切手を二つに裂き、琴子が踵を返す。と、
「いつ気づいた?」
もはや済んだこと扱いなのか、神威はこちら以上に感情の揺らぎが見られない。いや、ある。ニヤニヤと嗤うその様は実に愉しげだ。
琴子はテーブルにリボルバーを置くと、チラリと横目に神威を見て、
「ルールのことですか?」
「もちろん」
「いつかと問われると最初からとしか……。今回のゲームは神が考案したものですよね?」
「うん、ママが考えた。よくわかったな」
「以前に神のゲームを経験していますからね」
「経験してるから?」
「さすがに学習しています、という意味です」
苦笑い気味にそう言って、琴子は奪われていた武器を身につけながら答え合わせを始めた。
今回のゲーム。結果だけ見ると、テキサスホールデムで負けた琴子が、何故か勝った側である花子を撃ち殺した、という格好になるわけだが、そこに至るまでのプロセスは単純ではない。
このゲームはプレイヤーに対し、実に難解な駆け引きを強いる作りとなっている。
「最初に違和感を覚えたのは精算方法の説明部分です」
あの時、神威はこう話した。
『2発賭けて負けたら2発。オールインしたなら6発。賭けた数の弾丸をリボルバーに込める。負けた奴は一度引き金を引いてもらう。
なーに、余裕だって。スカったら負けはチャラだ。賭けた弾はリセットされて2回戦に進める。でももし、運悪くアタリを引いちゃったら……、BAN! だ。
よーするにチップはロシアンルーレット方式での毎戦精算。とーぜん引き金を引かないってのはナシだ。拒否したり逃げたりしたら、カムがぶっ殺すのでそのつもりで。
どちらかが死ぬまでこれを繰り返してもらう。最終的に相手を殺した方の勝ちだ。説明はいじょー。わかったか?』
「この説明を受けた時、私はこう思いました。“このゲームはいかに大きく負けて、相手を確実に撃ち殺せるか”を競うゲームであると」
神威の説明を箇条書きに起こすとこうなる。
・敗北時、負け額と同数の弾丸をリボルバーに込める。
・負けた側は一度引き金を引く。
・引き金を引くことを拒否することはできない。
・チップはロシアンルーレット方式での毎戦精算。
・当たりを引かなければ賭け額はリセット。次戦に進む。
・どちらかが死ぬまでテキサスホールデムを繰り返す。
・最終的に相手を殺した側の勝利。
「カムイさんはただの一度も“引き金を引く対象”を指定していません。どこに銃口を向けるべきか。対象はおろか、身体の部位さえ指定していません」
「言ってないけど、ロシアンルーレット方式で精算するって言ったじゃん。自分の頭ぶち抜くもんだって相場は決まってんだろ?」
「確かに。しかしその点こそが、このゲームで最も意地の悪い部分であると言えます」
要するに神威の説明は、ロシアンルーレットがどういうものであるか、プレイヤーが正しく理解していることを前提にしている。ほんの少しだけ言葉足らずなのだ。
琴子は神様のゲームを通じていくつもの後悔を覚えている。
その中の一つに『神との読み合いという視点を欠いた』ことが挙げられる。
この苦い経験が今回生きた。
「――ロシアンルーレット方式での毎戦精算、という表現は不親切ではないでしょうか」
「そうかあ?」
神威の言う通り、実際のところ彼女はロシアンルーレットの大部分を説明している。
弾を込め、引き金を引く。引く者はどこに弾が込められているのか把握できないまま、引き金を引かなくてはならない。説明としてはほぼマルだ。
しかし、
「ですがこの説明。手前のテキサスホールデムの説明と比較すると、違和感が残ります。
テキサスホールデムの時は実際にカードを用い、ゲームの最初から最後までシミュレートまでしてみせたのに、ロシアンルーレットについては口頭のみ。その口頭説明にしても、肝心要である“引き金を引く対象”の説明が欠落しています」
ここで琴子は神の関与をなかば確信した。
「ルールに対して“あそび”を設けるのは神の常套手段です。ああ、今のは悪口じゃないですからね?」
「わかってるよ」
つまり特定のルールに対し、プレイヤーに“解釈の余地”を持たせるということ。
この“あそび”こそが今回のゲームの本質なのだ。別の言い方をすると、神の敷く正しいルールを探り当てるゲームと表現してもいいだろう。
『わかっています! 私はただ、このゲームの本質は“神様の御心《みこころ》を正しく理解すること”だと申し上げたかっただけです!』
先ほど琴子が口にしたセリフの所以だ。
あそびの存在がこのゲームに対してどういう効果をもたらすのか。
ゲームに深みが増す。幅をもたらす。難解にさせる。
プレイヤーに『相手がどう解釈しているのか』を思考させるからだ。
考慮すべき点はいくつもある。
・説明が欠落しているのは意図的なものか、それとも単なる神威のミスなのか。
・相手に向けて引き金を引くことが、ルール違反に該当するのか。
・ルール違反であれば、神威に処分されるのか。
・相手は同じ疑問を抱いているのか、それとも気づいたのはこちらだけか。
神威に真意を問うことなどできようはずがない。琴子であれ、花子であれ。
もし自分だけが気づいていて、且つ、相手を撃ち殺すことが認められているなら、勝利条件が大きく変わる。認識の不一致は圧倒的なアドバンテージだ。
神威に正確な情報を求めることは行いとしては正しいし、本来なら公正な措置だと言える。
しかし、このゲームは真実命を賭けねばならない。
勝機を自ら手放すなんて馬鹿のすることだ。相手を出し抜くのが当然なのだ。
故にプレイヤーはテキサスホールデムの読み合いに加え、ルールの真実、さらにはルールに対する互いの解釈まで探らねばならない。
「状況は難解至極に複雑怪奇。解釈というエッセンスを加えることで、ゲームの展開に深みを持たせる。神好みのやり口です。ああ、ちなみに今のも悪口では……」
「だからわかってるって! お前、保身ばっかだな!」
琴子が花子を撃ち殺した――、なんて結果だけで語れる簡単な話ではない。そこへ至るまでが肝なのであって、事実、琴子は経過のなかで相当苦労をされられた。
ゲーム開始当初、琴子は『自分だけが気づいて』いて、且つ『相手に向けて引き金を引いても良い』という仮説を元に行動指針を立てた。
結果的にこの仮説が正しかったわけだが、もちろん琴子は運任せで花子を撃ち殺したのではない。きちんと根拠を積み上げたうえで行動を起こした。
「最短で勝つには、最低でも二度の敗北が必要でした」
一戦目の敗北は、仮説の正否を確かめるため。
二戦目の敗北は、実際に花子を撃つためだ。
「そう方針は立てたものの、開幕早々にバレッツでしょう? 正直頭を抱えました」
琴子は一戦目に於いて二つの失敗を犯している。
一つ目はバレッツが来たことの意味を履き違えたことだ。
手札を開けた瞬間、琴子は真っ先にイカサマを疑った。
臭う。きな臭い。わざと琴子に『勝たせようとしている』ように思えてならなかった。
琴子に良い手を握らせ、勝負させて、実際に勝たせてしまう。
だが、いざ精算となったとき、勝ったはずの琴子が撃ち殺されてしまうといった具合だ。
故に琴子はイカサマの有無、及び関与している者の切り分けを行おうと考えた。
この試み自体は成功している。バレッツを明かしたことで花子の関与はほぼ払拭できた。が依然、神威への嫌疑は晴れないままだ。
「そんな矢先に花子さんのレイズ攻勢です」
「なるほどなあ、逆手に取られたって思ったわけだ」
これが一戦目二つ目の失敗。
琴子は花子のレイズ攻勢の意図を読み違えた。
だがこの件に関しては、今振り返ってみても仕方のないことだったと思う。
当初から花子がルールの解釈に気づいていたかはさておき、バレッツを明かした意図が、花子の反応を見るためであったことを看破されたと考えるのが自然だ。
そのことを材料に、花子は色々と連想できたはずだ。
琴子がイカサマを疑っていること。誰の仕業か突き止めようとしていること。バレッツが来ている理由。無論、花子は自分が関与していないことを知っているわけで、ならば当然の帰結として、花子は『神威の仕業』だと考える。
共通カード4枚目が開かれていたあの時、『Aスリーカード』が成立している琴子に対し、花子が作り得る最高役は『4・10・6』いずれかの『スリーカード』。花子の負けが決まっていた。
そんな状況下で花子はレイズしてきた。それも都合3発もだ。
必然、琴子の目にはこう映る。
花子のルールの解釈は琴子と同様であり、かつ彼女はバレッツを明かしたことを逆手に取って、意図的に負けようとしているのだ、と。
もし琴子がコールすれば、花子に5発の弾丸が込められた銃を握らせることになってしまう。
花子がこちらに向かって引き金を引いたなら、文字通り十中八九の確率で殺られることになる。
そんな致命的な状況を、琴子が許容できるわけがない。だから琴子は降りるしかなかったのだ。
「でもそれって、円成寺の勘違いだったんだろ? じっさいハナは撃たれちゃったんだし」
「そうなります。まあ、そのお話は後に回すとして――」
結果的に琴子は一戦目を落とすことになった。
それ自体は予定通りだ。琴子はこの敗北を通じてルールの解釈の裏を取るつもりでいた。
具体的には『負けた側が、勝った側に向けて引き金を引くことが許されるのか』を確かめることだ。
確かめる方法はシンプルだ。
弾込めを終えた後、三人の間でこんなやり取りがあった。
『これで精算の準備はかんりょーだ。一分以内に引き金を引け』
『思っていた以上に公正な措置ですね』
『だから言ったろう? カムはちゅーりつこーせーだって』
『当たりを引くと思いますか?』
『引かないんじゃないかしら』
『三分の一ですものね』
このとき琴子は、弾が込められた銃を“手で遊びながら”会話に興じた。
その間、琴子は数回に渡って銃口を花子に向けたが、神威は一度も咎めなかった。終始こちらを注視していたにも関わらずだ。
そのことを以って琴子は『撃ち殺しても良い』と判断。しかしリボルバーに込められている弾はたったの2発。とても当たりを引けるとは思えない。
だから、
「自分の頭に向けてトリガーを引いたと」
「それが最良と判断しました。花子さんの誤解を定着させることができますし、そもあそこで当たりを引いてしまうくらいなら、どのみち私はこのゲームに勝ち残れないでしょう。その程度の女だったのだと諦めもつきます」
「まー、だいたいわかった」
神威はフムフムと頷いて、花子の亡骸に目をやった。
「しっかし、ハナってばなにを思ってレイズしたんだろうな」
「どうでしょう。もう死んでしまっているので本当のところは判りませんが……」
未解決な点が一つ残っている。
一戦目の終盤、花子は何を意図してレイズ攻勢をかけたのかということだ。
琴子は映画の登場人物を『琴子・花子・神威・神』の『四人』だと仮定した一方、花子はそれを『琴子・花子・神威』の『三人』だと認識していた。
花子のレイズ攻勢を受け、危うく琴子は、花子が四人と認識していると誤認しかけたが実態は違った。
「これは推察に過ぎないのですが」
ヒントはある。
一戦目、琴子が降りたあと、花子は得意げな顔でこう言った。
『勿体無いことをしたわね。もし引かずにコールしていたら、私を殺せていたでしょうに』
琴子が強烈な違和感を覚えた言葉だ。
両者の間で認識の食い違いが生じていなければ、絶対に出てこないセリフなのだ。
どう考えてもおかしい。琴子はコールすれば自分が撃たれると思っていたのに、花子は自分が殺されていたと言う。
「花子さんは、私とは別の視点で深読みしたのではないでしょうか」
「別の視点?」
花子の側に立って事実関係を整理すると、見えてくることがある。
・琴子のバレッツがブラフではなかった。
・琴子は過剰と思えるほどイカサマ行為を警戒している。
・5枚目共通カードが未だ開かれていない。
「花子さんのレイズ攻勢にコールすれば、私が殺されてしまう――、つまりこのゲームそのものが出来レースであると、私が誤認するだろうと考えたのではないでしょうか。そのためのレイズだったと」
「ん? んん……?」
花子はこう考えたのかもしれない。
琴子はイカサマを半ば確信し、過剰なまでに恐れている。そんな彼女にレイズ攻勢をかければ、琴子はどう考えるか。
花子の負けが決まっている状況下でのレイズ。必然、琴子は花子の意図を読み解かねばならなくなる。
が、論理的な説明がつく事由など存在しない。突っ張られたら花子は負けるのだ。
そんな不合理なレイズに意味を見出すとすれば、「ハナっからこのポーカーの勝ち負けに意味などない」くらいしか思いつかない。
つまりは出来レース。ポーカーの勝敗に関わらず、琴子は殺されてしまうことが決まっている。
もし猜疑心の強すぎる琴子にそう思い込ませることができたなら、琴子は降りざるを得ない。勝った途端に、殺されてしまう恐れがあるからだ。
琴子は一旦降りて、状況を打開するための時間稼ぎをするだろう。
「ようは猜疑心という側面で、私の考えを深読みしたのではないかと。まあ、今となっては真相は判りませんが。ともかく私は、花子さんのあのセリフを以って、自分の誤解と、彼女の誤解の両方に気づけたというわけです。もっとも――」
言いながら、琴子は床に転がっている二枚のカードを拾い上げた。
琴子は苦笑しつつ、クシャクシャになったカードのシワを丁寧に伸ばし、
「このゲームにおける最大の敵はわたくし自身だった――、というのが笑えないのですけれど」
テーブルの上にそっと置かれた二枚のカード。
それを見た神威が「やっぱりな」と鼻を鳴らし、侮蔑満載の目で琴子を見る。
「円成寺、マジ汚ねー」
ですね、と琴子は愛らしくはにかむ。
琴子が捨てた手札は『ハートKA』。
一戦目のバレッツといい、二戦目のロイヤルストレートフラッシュといい。イカサマでもなんでもなく、ただ単に琴子が豪運なだけだったというオチ。
どうやら神ではない何かは、何が何でも琴子に勝たせるつもりだったようだ。
けれど、負けるが勝ちのこの勝負。琴子にすればいい迷惑だ。
「天に愛されるというのも困りものです」